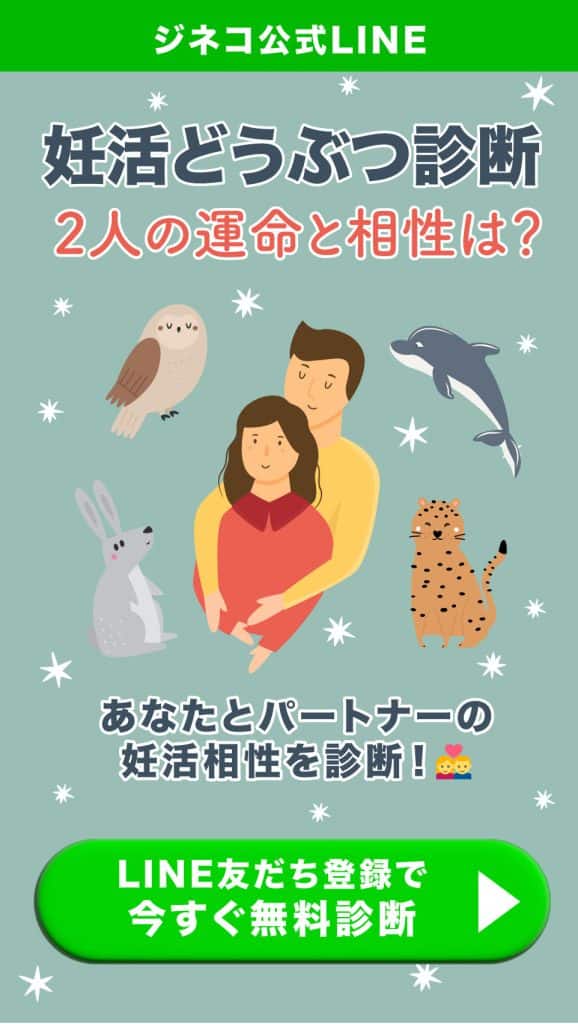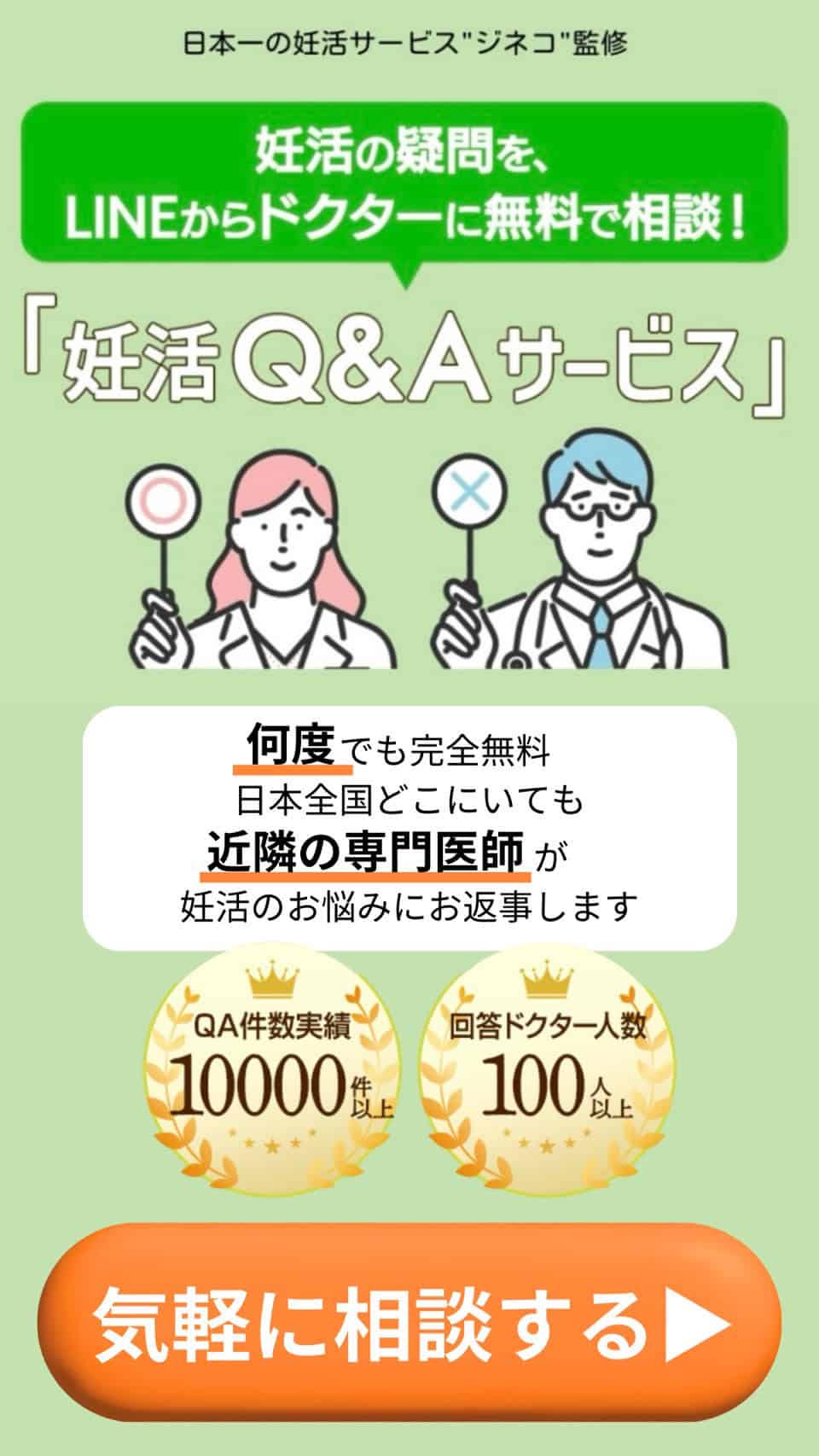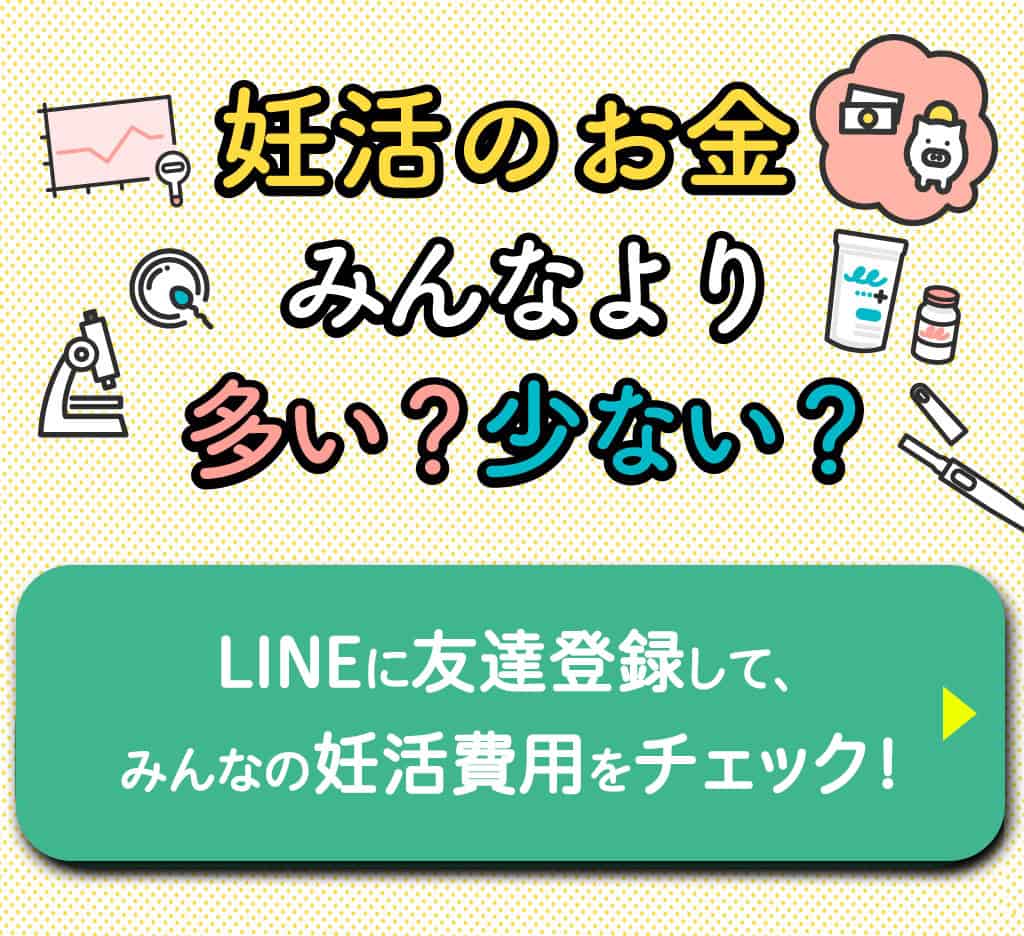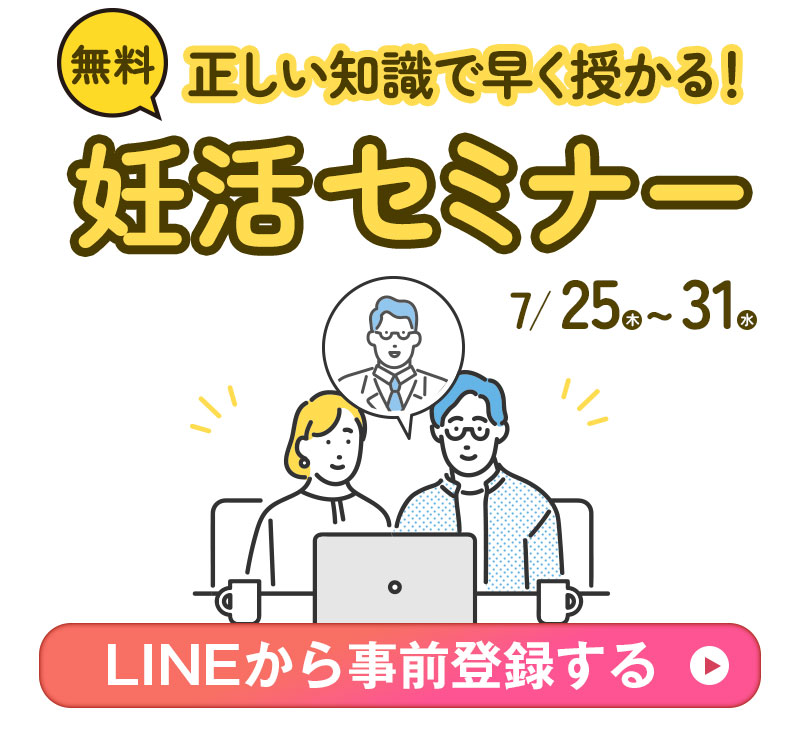新首相が不妊治療の助成金を大幅に増額するよう、厚生労働大臣に要請したというニュースが最近注目されました。現在でも国や都道府県の助成金の支援はあるものの、まず不妊治療そのものの値段を知りたい方もいるでしょう。そこで、秋山レディースクリニックの秋山芳晃先生に保険の適用範囲や自費の負担について伺いました。

不妊治療は保険適用される?
まず、不妊治療の保険適用範囲については、お住まいの地域やクリニックの方針によって微妙に変わることもあるので、ここでは当院の例でお話ししたいと思います。
タイミング指導や人工授精の場合、排卵障害に対する排卵誘発剤の使用や卵胞計測のための超音波検査・ホルモン検査は、保険で対応することが可能です。ただし、これについては回数の制限があるため、たとえば超音波検査を 回以上すると、そこからは保険がきかなくなります。そして、人工授精の際に精子を子宮に入れる処置については、自費診療となります。
不妊治療をしていると「混合診療」という言葉を聞かれる方もいるかもしれません。「混合診療」とは同一診療日に保険診療と自費診療を同時に行うことをいいます。
たとえば排卵障害の再診料は保険適用内だけれど、先にお話しした回数を超えた超音波検査は自費診療となってしまうので混合診療となり、これは原則として禁止されています。
混合診療が禁止されているのは本来、保険診療に必要な医療が提供されているのに、保険外の診療を行い、その負担を患者さんに求めることが一般化し、患者さんの負担が不当に拡大するおそれがあること、安全性・有効性が確認されていない医療が保険診療とあわせ実施されることによって科学的根拠のない特殊な医療の実施を助長するおそれがあるからです。
そのため、どうしても自費診療になってしまう患者さんの場合、なんとか負担を減らして差し上げたいと当院でも、さまざまな工夫をしているのが現状です。
ステップアップし、体外受精や顕微授精になると、はじめからすべて自費診療になります。

一般的な治療のめやすはどのくらい?
初診の費用
月経周期のタイミングによりますが、子宮卵管造影検査を除くスクリーニング検査(抗精子抗体検査・AMH・酸化ストレス検査・ビタミンD濃度など)約3万円
2回目以降の検査費用
・ タイミング指導に必要な超音波検査のみ 自費の場合約2千円
・ 子宮卵管造影検査 1万4千円
人工授精
1万7千円(当日の精液検査と抗生物質を含む)
体外受精
排卵誘発剤の費用などを含み約60万円
顕微授精
排卵誘発剤の費用などを含み約万円〔体外受精に含まれる治療・検査内容ホルモン検査・子宮鏡検査・超音波検査・採卵(麻酔にかかる費用を含む)・胚培養および管理〕胚凍結・管理費 5万円(2年間)
胚移植 新鮮胚移植 5万円 補助孵化(アシステッド・ハッチング)3万円 凍結融解胚移植(ホルモン補充の薬剤費含む)約万10~15万円
助成金は誰でも受け取れる?
助成金は、お住まいの地域によってさまざまな種類があります。国の「特定不妊治療費助成事業」からは、体外受精、顕微授精について助成金が出ます。

そのほか、都道府県、市区町村でも対策を行っています。どれも所得制限や年齢制限があるので、自治体のホームページなどで確認したり、クリニックのカウンセラーからもぜひ、アドバイスを受けてみてください。今年はコロナ対策で方針が変更されたりもしているので、国や自治体の助成制度をぜひ有効に使って治療に臨んでください。