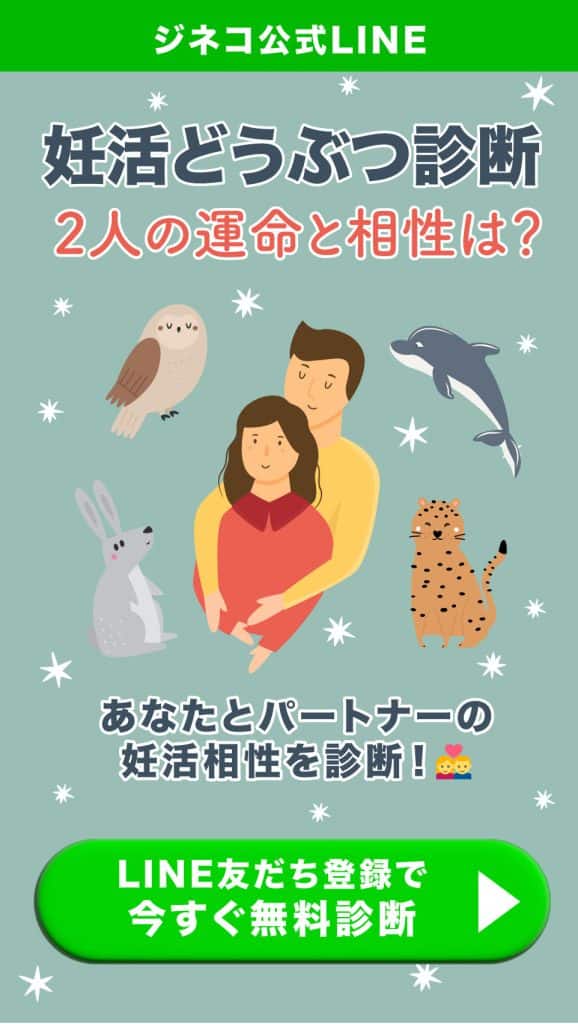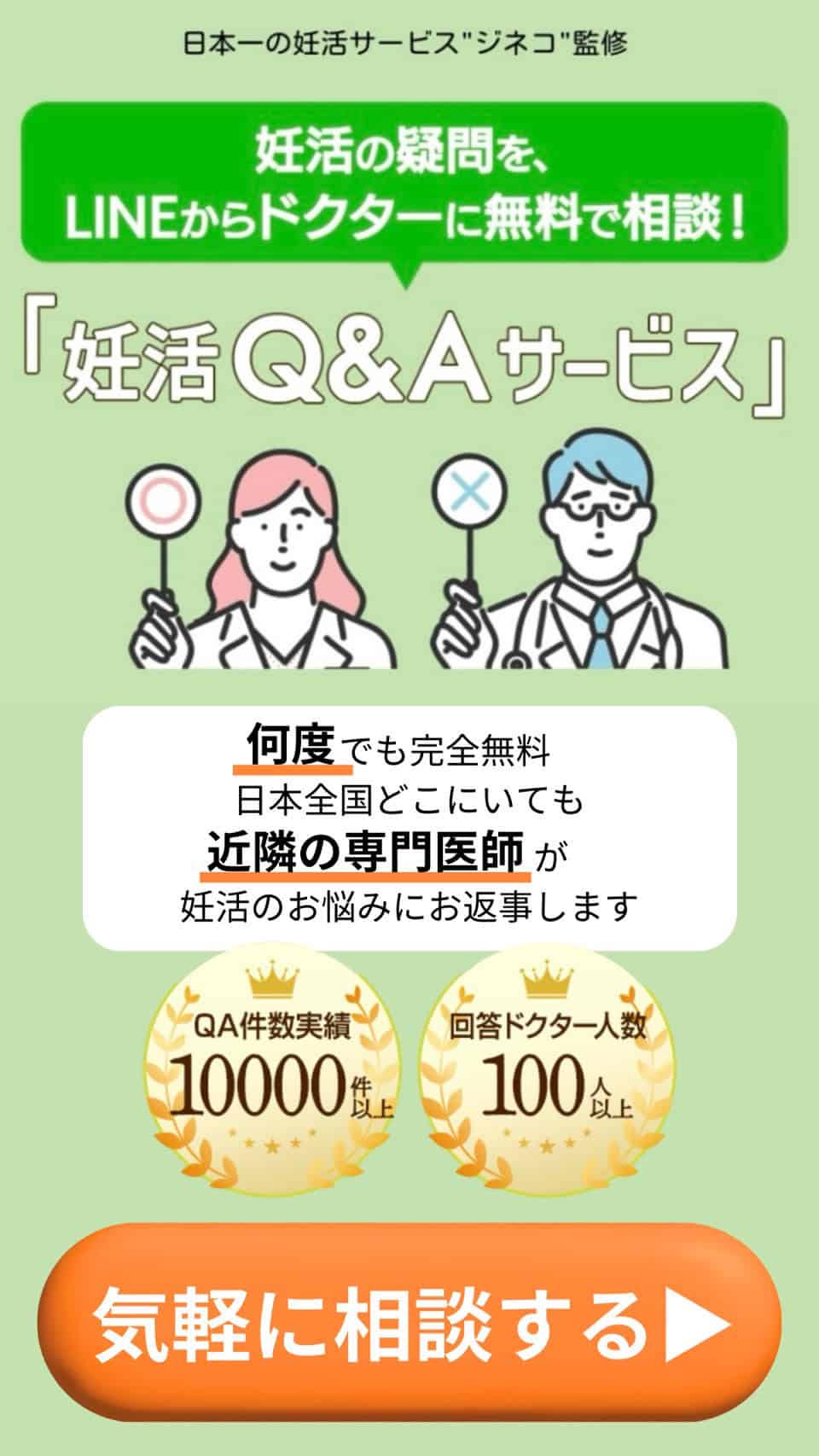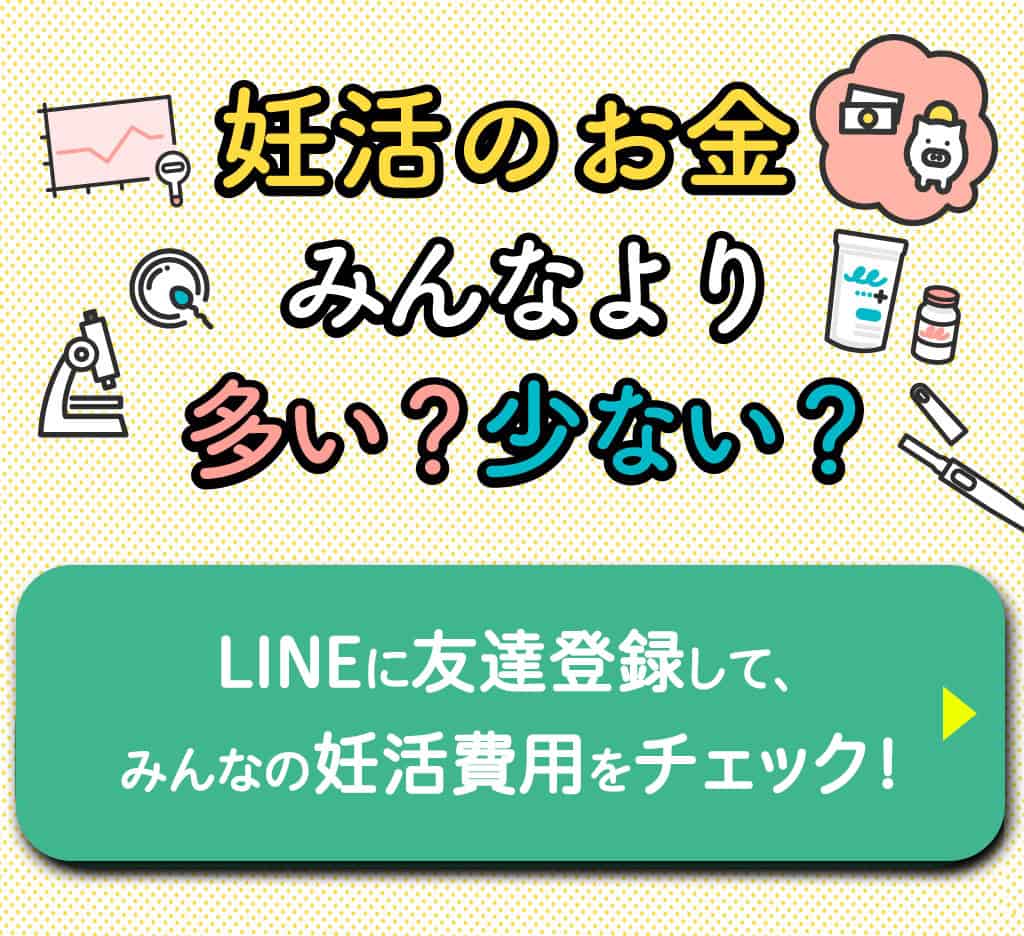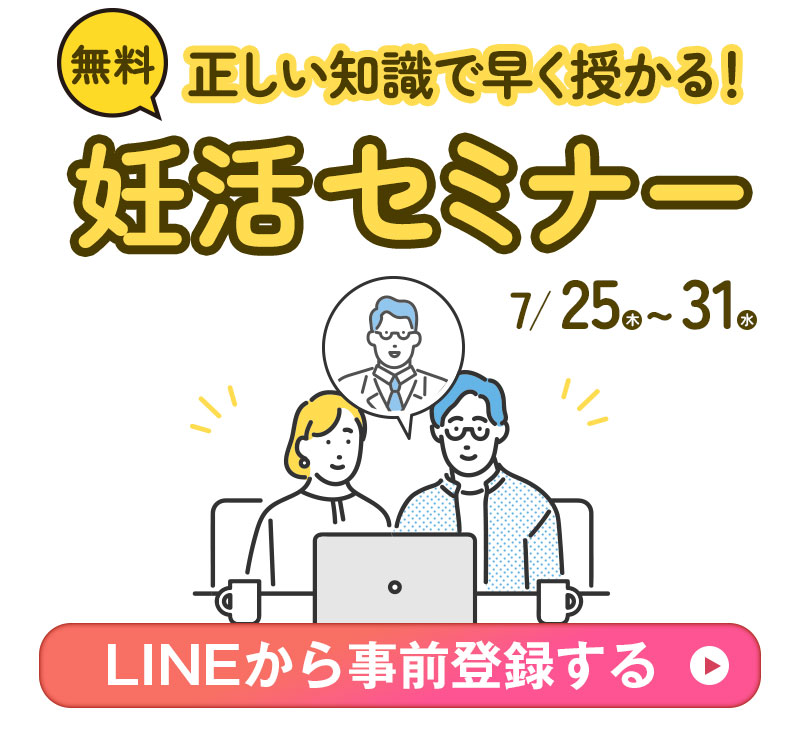▶︎体外受精への夫の発熱の影響は?
治療2年目。1回目の体外受精で着床しましたが化学流産、2回目は顕微授精での受精卵が育たず培養中止となりました。2回目は採卵前日に夫が38 度の発熱。もともと精子の直進運動率が0 ~ 4%と低く、正常形態率が2%ですが、発熱後はさらに運動率が低めでした。高熱は精子の数や質に影響し、影響のピークは1カ月後と聞きました。次回採卵はちょうど発熱1 カ月後にあたり、体外受精を予定しています。見送るべきでしょうか。

札幌医科大学卒業。2014 年より神谷レディースクリニック勤務。日本生殖医学会生殖医療専門医。日本産科婦人科学会認定専門医。日本抗加齢医学会専門医。
化学流産、培養中止の理由はどんなことが考えられますか。
岩見先生● 1回目の受精卵は胚盤胞まで育ち着床できたわけですから、着床不全を除外すると、着床後の受精卵成長にかかわる染色体因子が考えられます。42歳の胚盤胞は約80%に染色体異常があるとされています。培養中止になった2回目の受精卵にも染色体異常があった可能性がありますね。受精後も細胞分裂の過程で重大な染色体異常があると、それを修復・排除できず、分裂が停止してしまうと考えられています。
一方、精子側の要因としては精子のDNA損傷が挙げられます。DNA損傷は初期胚から胚盤胞への到達率を低下させるといわれています。
発熱は精子の質に影響を及ぼすことがあるのですか?
岩見先生● おっしゃる通り、高熱(38・5℃以上)は、精子の数・運動率・形態・DNAの質に一時的な悪影響を与えるといわれ、発熱後早期でも運動率や精子濃度の低下がみられることがあります。そのため、精子のDNA断片化などの機能低下が、受精卵の分割停止に影響した可能性はあるかもしれません。
高熱の影響がどのくらい続くかですが、精子所見の急性変化は発熱1~2週間後から顕著に現れ、2~3カ月かけて回復するといわれています。個人差もあるため、高熱から1カ月以上経っていれば、一度精液検査で現状確認してみることをおすすめします。
精子が回復するまで採卵は見送るべきですか?
岩見先生●卵巣の状態が良ければEさんに合わせた採卵をおすすめします。精液が改善して体外受精を希望される場合には、精子側のDNA損傷などのリスクを評価するため胚盤胞まで培養されるとよいでしょう。
Eさんの場合、顕微授精をする際、先進医療技術であるPICSIやIMSI、マイクロ流体技術を用いた精子選別などを利用し、DNA損傷が少ない良好な精子を選別する方法も検討してみてください。
排卵誘発剤は低刺激のものをお使いと推察しますが、そうであれば刺激法を変えて1周期で複数個の採卵を考えてはいかがでしょう。複数個あればそれだけチャンスは広がります。着床した受精卵を得られた経験があるのですから、毎月のチャンスを十分に生かしていただきたいと思います。