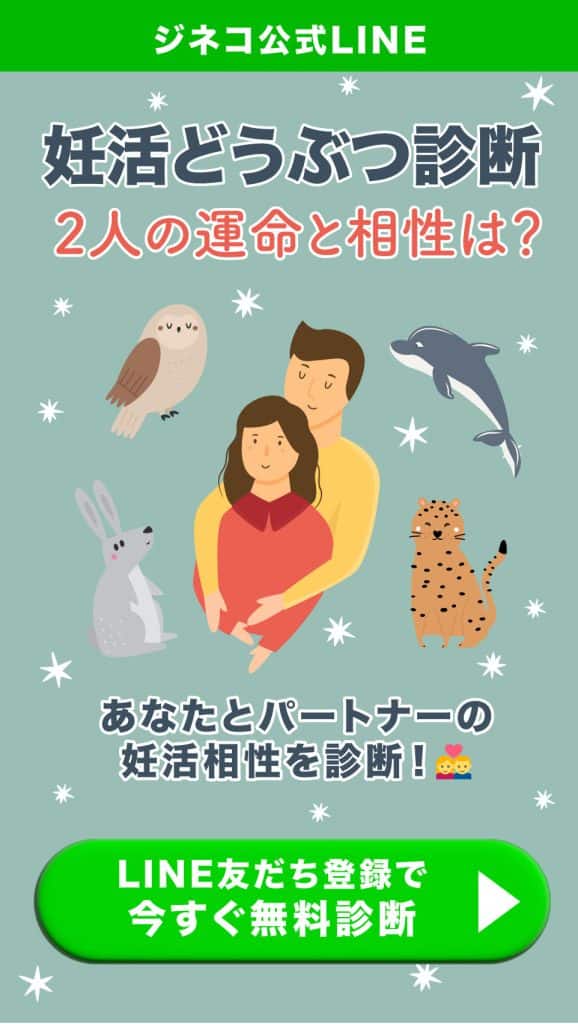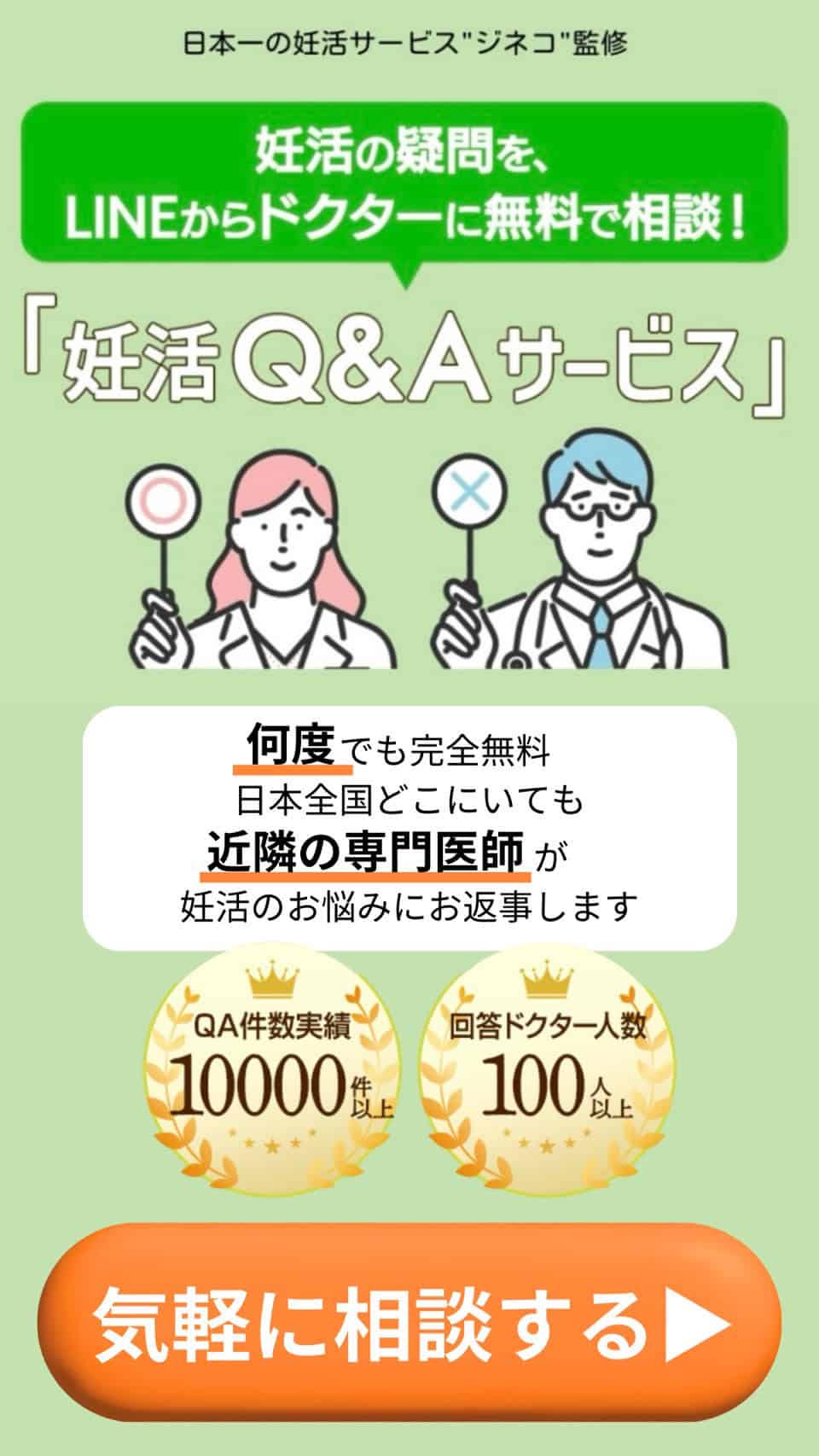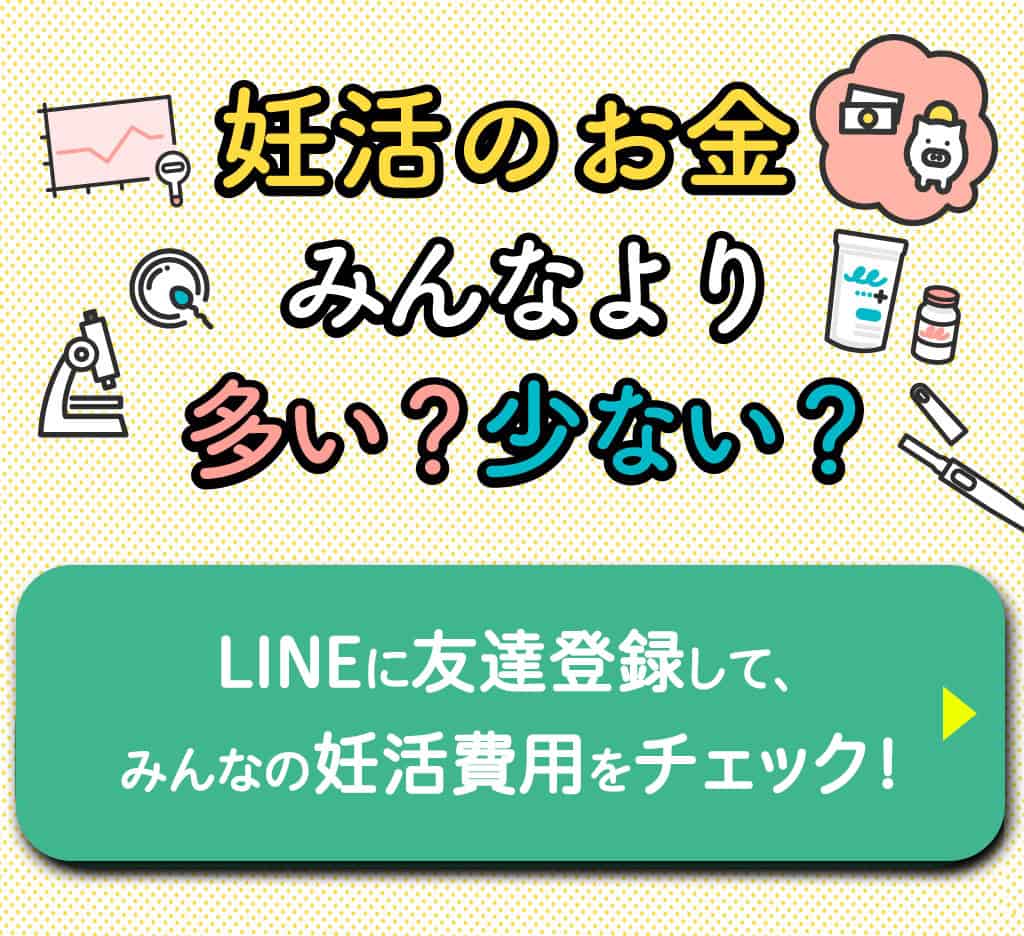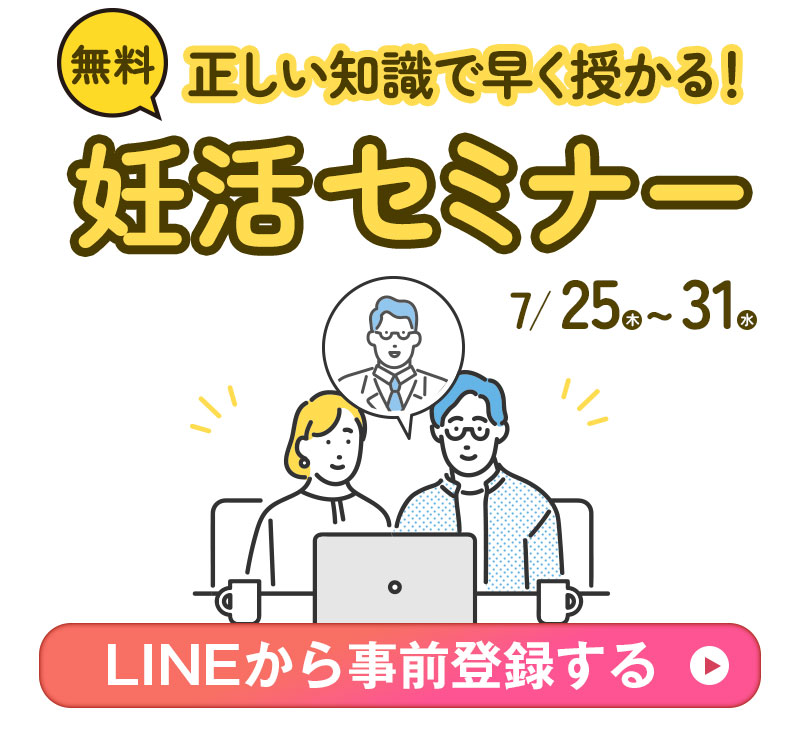妊娠を考えた時、まず頭に浮かぶのは基礎体温を 測ることだったりしませんか?
でも、毎日、体 温を測るのって面倒ですよね。
そもそも、「基礎体 温からは何がわかるの?」「治療に基礎体温表は必 要?」と、意外と知らないことが多いもの。
今回は、 体温の測り方や婦人体温計の選び方まで、基礎体 温についてのいろいろなお話を内田クリニックの 内田先生にお聞きしました。

基礎体温表からは、何がわかるのでしょうか?
まず、基礎体温表は何のためにある と思いますか?
基礎体温表で最もわ かることは排卵しているかどうかです。
排卵は卵巣の働きなので、「卵巣の働きがどんな状態か?」をグラフで見ることができるのが基礎体温表の一番の基本として考えましょう。

体温の低い時期と高い時期にしっかり別れていれば排卵していると見れます。
低い日ばかりが続いていれば排卵していないことがわかるわけです。基礎体温をつけておられる方でよく勘違いされているのが、基礎体温をつけながら排卵時期を推測しようとされている点です。
基礎体温の明日も明後日も未来の体温はわからないので、基礎体温の測定では排卵の推定はできないのです。
グラフ化された基礎体温表で、体温が高くなったことを確認できて初めて排卵したことがわかります。
したがって、あとで振り返った時に、「ああ、この日が排卵だった」と初めてわかるのです。
繰り返しますが、基礎体温表をつけていても排卵のタイミングを推測することはできません。
この勘違いを皆さんにはぜひ知っておいていただきたいです。
基礎体温表では月経周期の記載を忘れないようにしましょう。
生理が始まった日が1日目です。そこから数字を打ち、次の生理がきたら新たに1日目に戻ります。
すると、月経周期や体温の変化が一目でわかり、排卵障害、月経周期異常の有無が見えてきます。
さらにSEXのタイミングを書き入れると、排卵のタイミングとSEXのタイミングが合っていたかがわかるようになります。
SEXの回数が少なければ、「回数を増やしてみましょう」と伝えることもできます。
治療を始める前から基礎体温表を記録したほうがいいでしょうか?
治療を始める前 3 カ月分の基礎体温表は、産婦人科の先生にとって役立つ情報になるので、つけたほうがいいと思います。
治療が始まると診察や血液検査の情報も加わるので必要ないことが多いのですが、途中で治療を休む場合は、その間の卵巣の状態を知るためにつけておくといいですね。
基礎体温の測り方について教えてください。
基本は朝、目覚めた時ですが、測る時間帯は厳密でなくてもいいと思います。
寝て目が覚めたら、そこがソファの上でも、午前 10 時や午後の3 時でも測りましょうと伝えています。
測定できない日が 1 ~2日くらいなら線でつなげばいいのですが、3 日・ 4 日と測らない日が続くと卵巣の働きを推定している基礎体温の本来の目的から離れる場合もあります。
できるだけ毎日測定をしてもらいたいので、「何時でも起きた時に測ればいいや」という気軽な考えでいいと思います。
そのほうがストレスなく続けられると思います。
婦人体温計はどのようなものを選べばよいのでしょうか?
WHO(世界保健機関)は2020 年までに水銀の廃止を決め、近年は世界中でデジタル体温計になりました。
デジタル体温計は推測体温計なので正確とは限りません。僕たちは水銀計で測ったグラフを知っているので、見ればデジタル体温計で測定したグラフとわかります。
水銀計に比べて、推測体温なので、どうしても測定値がバラバラしてしまいます。そのデジタル体温計は、人によって合うもの合わないものもあります。
また、体温がグラフの標準値より低い時には電池の減少も考えられますし、体温計のブランドを変えてみることもおすすめしています。
スマートフォンなどで基礎体温を記録するアプリも増えました。内田先生は、どう感じていますか?
デジタル体温計と連動したアプリは体温を入力したらグラフになるので、とても楽です。
でも、月経周期など細かな情報を入れるアプリにまだ出会っていません。
簡単にメモできるアプリがなければ、今は基礎体温アプリを記憶ツールとして考え、それを紙の表にアナログ的に記録する方法がいいとすすめています。
スマホのスケールではグラフの形と温度の変化がわかりにくく、排卵しているように見えないという問題があります。
iPadぐらいの画面サイズがあれば、拡大すれば、見えやすくなるので、基礎体温表として評価できる印象があります。
治療が始まり、薬を服用することで基礎体温に変化が生じることはありますか?
薬によって違いますが、ホルモン剤を使用したらあり得ます。
たとえば、クロミッドⓇを使うと服用中に体温が高くなったように感じることがあります。
でも、それは薬の影響・効果で体温が動いただけなので、気にしなくてもいいです。
最初からそうなる可能性がある前提で、治療が始まる場合もあります。
治療デビューした方へのメッセージをお願いします。
後悔しない決断ができるように情報を集め、その情報をご夫婦のなかで整理し、どう進んでいったらいいか意志をもちながら治療にのぞみましょう。
そして、わからないことがあったら遠慮なく聞くこと。
でも、あまり予備知識がないと何を聞いていいのかもわからないですよね。
当院では、初診で治療についての冊子をお渡ししています。それをご夫婦で読んでもらうと質問の仕方が変わります。
まずは情報をもち、二人で共有することだと思います。