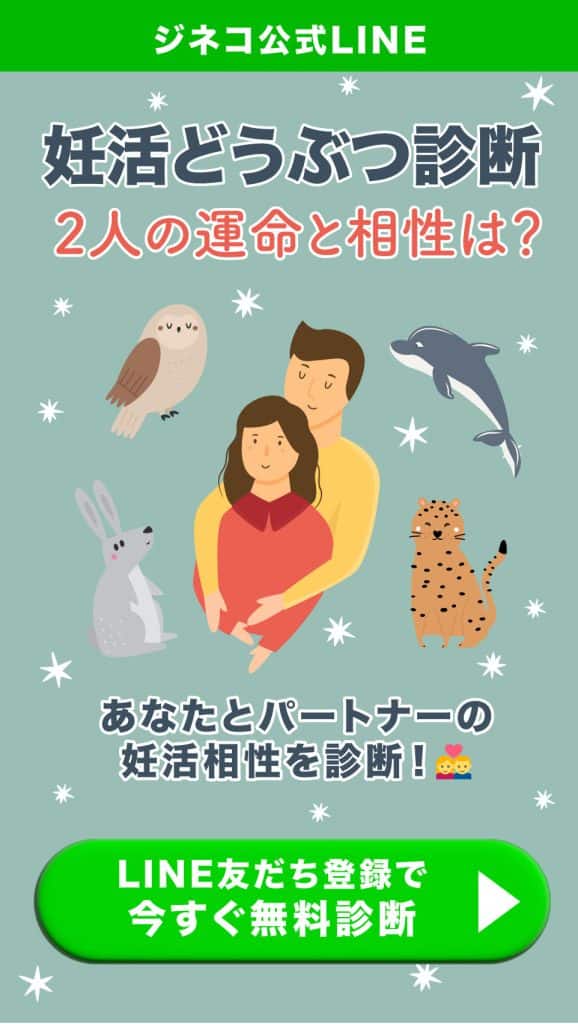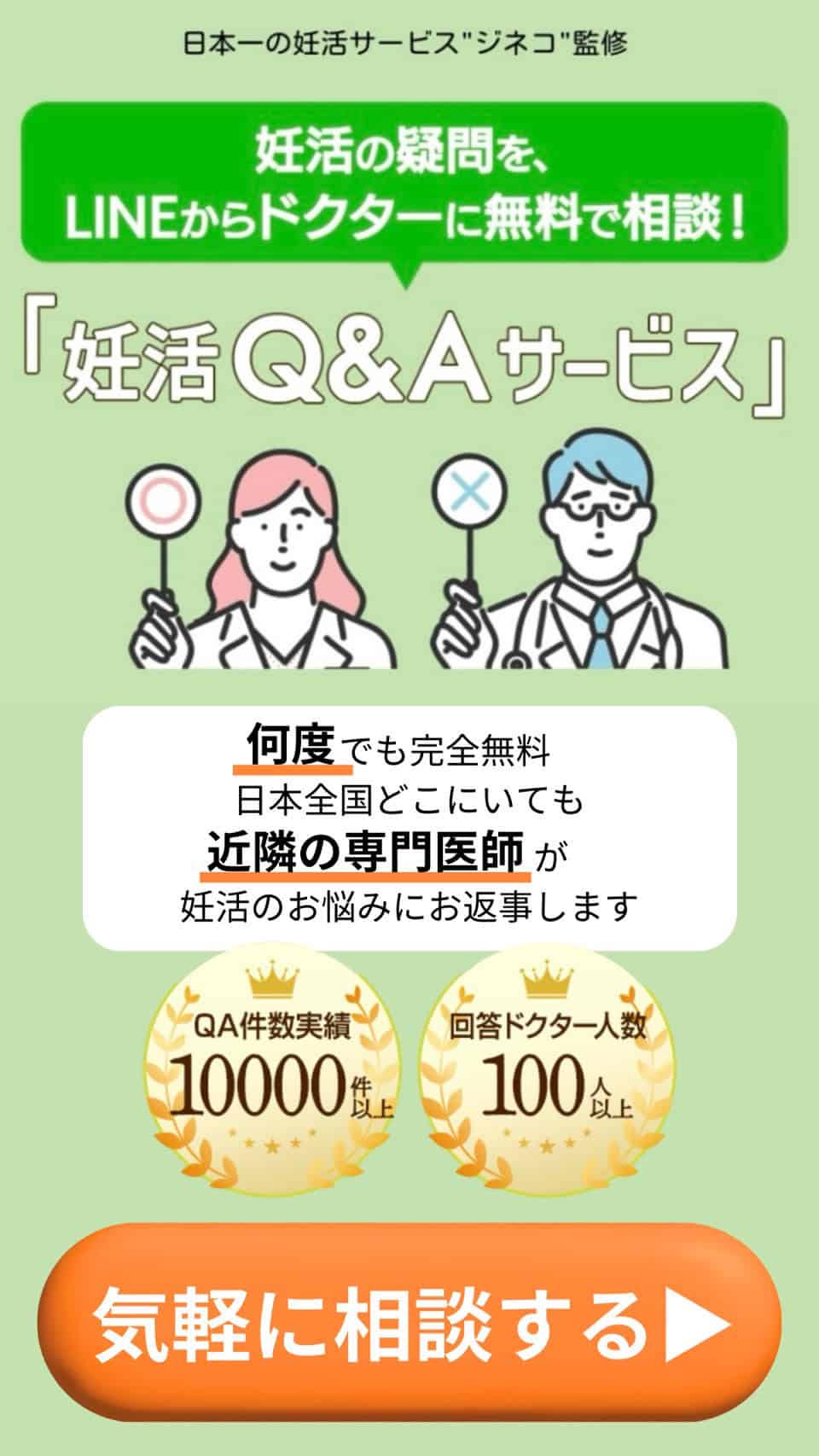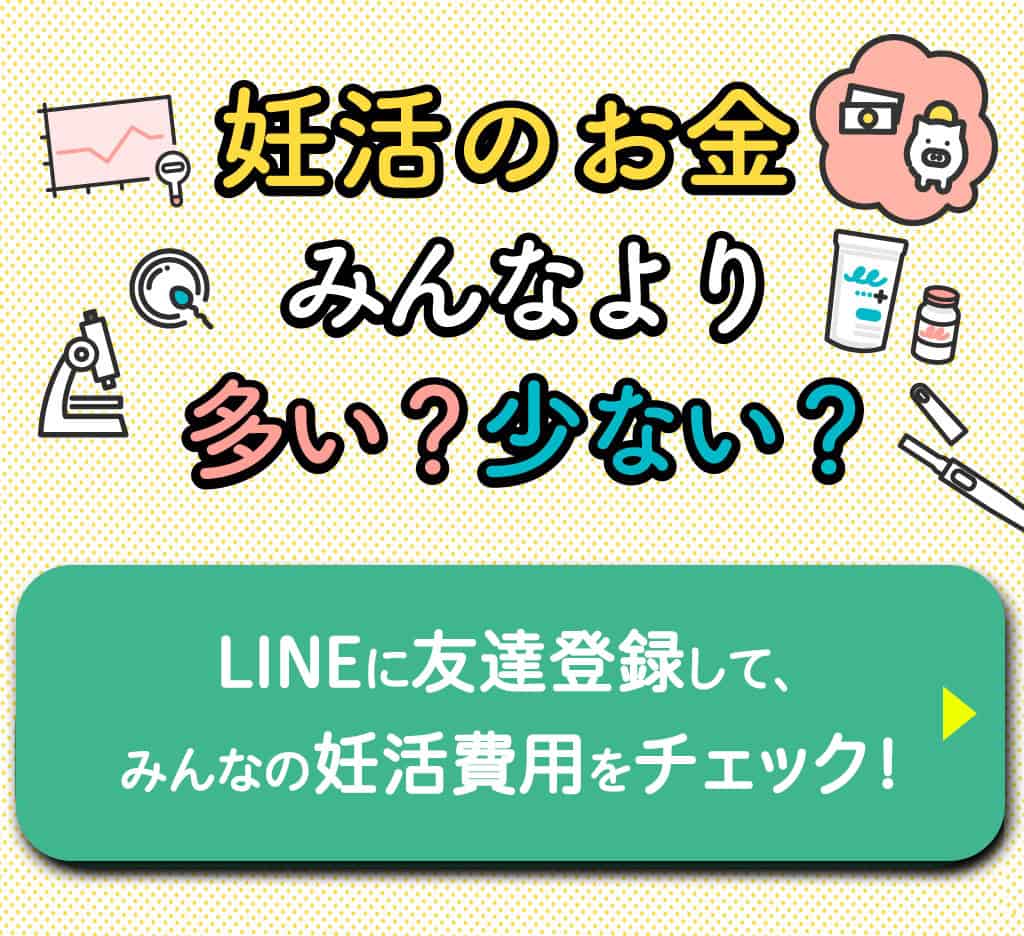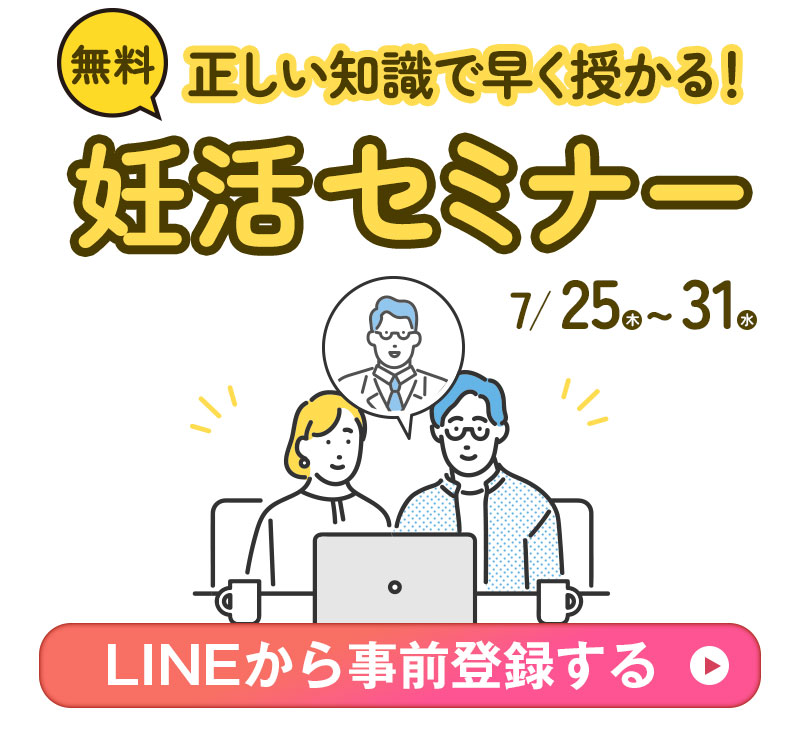あいさん(39歳)
人工授精前に21mmの卵胞を確認し、人工授精後にhCG5000を注射しました。
濃縮処理された精子は24時間受精可能、排卵は36時間後なのでタイミング的には今回は人工授精が合っていなかったように感じています。
排卵障害もあり、いつ排卵されたかもわかりません。
今まで採卵を5回繰り返していますが、4個~9個ほどしかできません。
胚盤胞になったのも一度のみ4BBで、それも妊娠には至っていません。
しかしながら、体外受精の合間には人工授精での妊娠もあり心拍確認もできています。
私には高刺激は向いていないのでしょうか。
体内では胚盤胞になるのに何故体外では胚盤胞にならないのかがわかりません。この場合は初期胚移植がよいのでしょうか。排卵障害もあり、ホルモン補充周期でなくては移植ができませんが、その周期に行う新鮮胚移植も有効でしょうか。
年齢も40歳に近づいてきていますが、このまま治療を続けて第二子が授かる可能性はまだありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
小川誠司先生に教えていただきました。
藤田医科大学 羽田クリニック 小川 誠司 先生
2004 年名古屋市立大学医学部卒業。2014 年慶應義塾大学病院産婦人科助教、2018 年荻窪病院・虹クリニック、2019 年那須赤十字病院産婦人科副部長、仙台ART クリニック副院長を経て2023年9月、藤田医科大学東京 先端医療研究センターの講師、2024年4月から准教授に就任。自費で最新の医療を受けられるという併設の羽田クリニックで患者さん一人ひとりの思いをかなえるべく診療も行っている。日本産科婦人科学会専門医。日本生殖医療学会専門医。
※お寄せいただいた質問への回答は、医師のご厚意によりお返事いただいているものです。また、質問者から寄せられた限りある情報の中でご回答いただいている為、実際のケースを完全に把握できておりません。従って、正確な回答が必要な場合は、実際の問診等が必要となることをご理解ください。
●あいさんの場合、人工授精のタイミングについて、どのような提案をされますか? 特に、 hCG5000の注射後の排卵タイミングについての見解をお聞かせください。
人工授精の投与前日あるいは前々日にhCGを投与しても、人工授精の当日にhCGを投与しても妊娠率は大きく変わらないというのが一般的な見解です。ただ、あいさんの場合、元々排卵障害を指摘されていますので、採卵と同様に、人工授精の前々日の夜にhCGを自己注射していただき、当日の朝に人工授精を行うのも良いと思います。また人工授精の翌日以降に、しっかりと排卵しているかどうかの確認を行うと、より良いように思います。
●あいさんの採卵回数と卵胞の数、胚盤胞の発育状況を考慮に入れた上で、高刺激法があいさんに適していると思われますか?
誘発方法の変更により、良好胚が採れる可能性はあります。採れた卵子の数に対して、年齢を考慮しても胚盤胞に至っている数が少ないと思いますので、中等度刺激など刺激方法を変更しても良いと思います。

●体内で胚盤胞に発展するのに対し、体外では胚盤胞にならない理由について、何か考えられる要因はありますか?
誘発方法が合っていないために良い卵子が採れていない、あるいは受精後の培養環境が合っていないなどが理由として挙げられます。誘発方法を変更したり、培養する培養液を変更したりすることで、胚盤胞への発生率を改善することに役立つかもしれません。
●排卵障害があるあいさんの場合、新鮮胚移植の有効性について教えていただけますか?また初期胚移植が適していると考えられますか?
排卵障害がある場合でも排卵誘発剤やhCGを使用することにより移植は可能です(低刺激法)。あいさんは、人工授精でも妊娠されておられますので、新鮮胚移植や、低刺激法などによる凍結融解胚移植を考慮しても良いと思います。また複数卵子が採れており、少ないですが胚盤胞にまで至っていることを考えますと、胚盤胞に至っていない胚は異常である可能性が高いと思います。初期胚移植では胚を選別できないまま移植することになりますので、現状では初期胚ではなく、引き続き胚盤胞移植をお勧めします。
●一度妊娠経験があり、現在 40歳近くで第二子を望んでいる状況を考慮に入れて、今後の治療方針や妊娠可能性について、先生の見解をお聞かせください。
妊娠のご経験があることは非常に大きいことで、今後も妊娠される可能性は十分にあります。ただ同じやり方を繰り返すだけでは、結果につながらないことも往々にしてありますので、先に記載した通り、誘発方法、培養環境の変更や、移植方法の変更についてもぜひご検討いただければと思います。