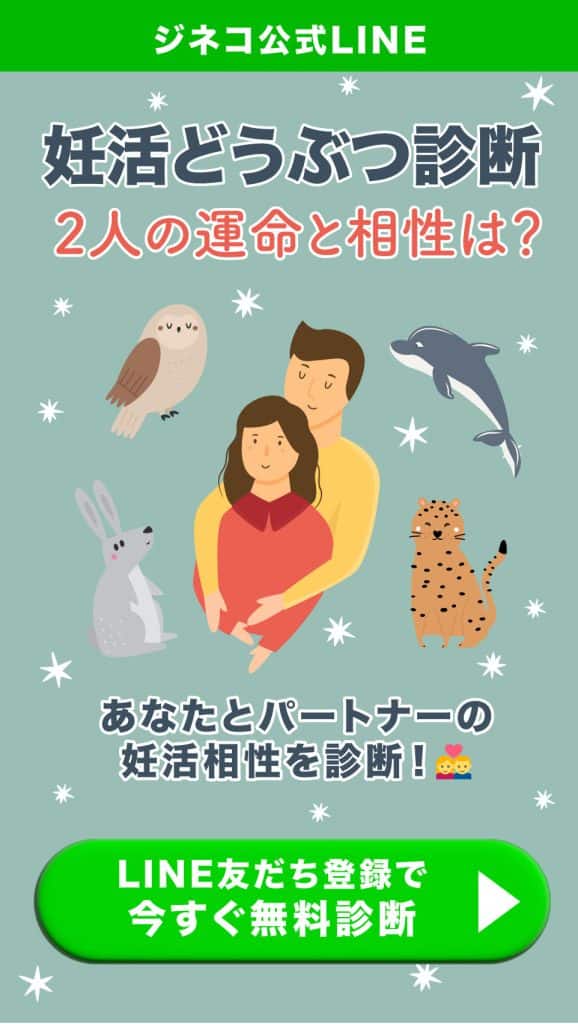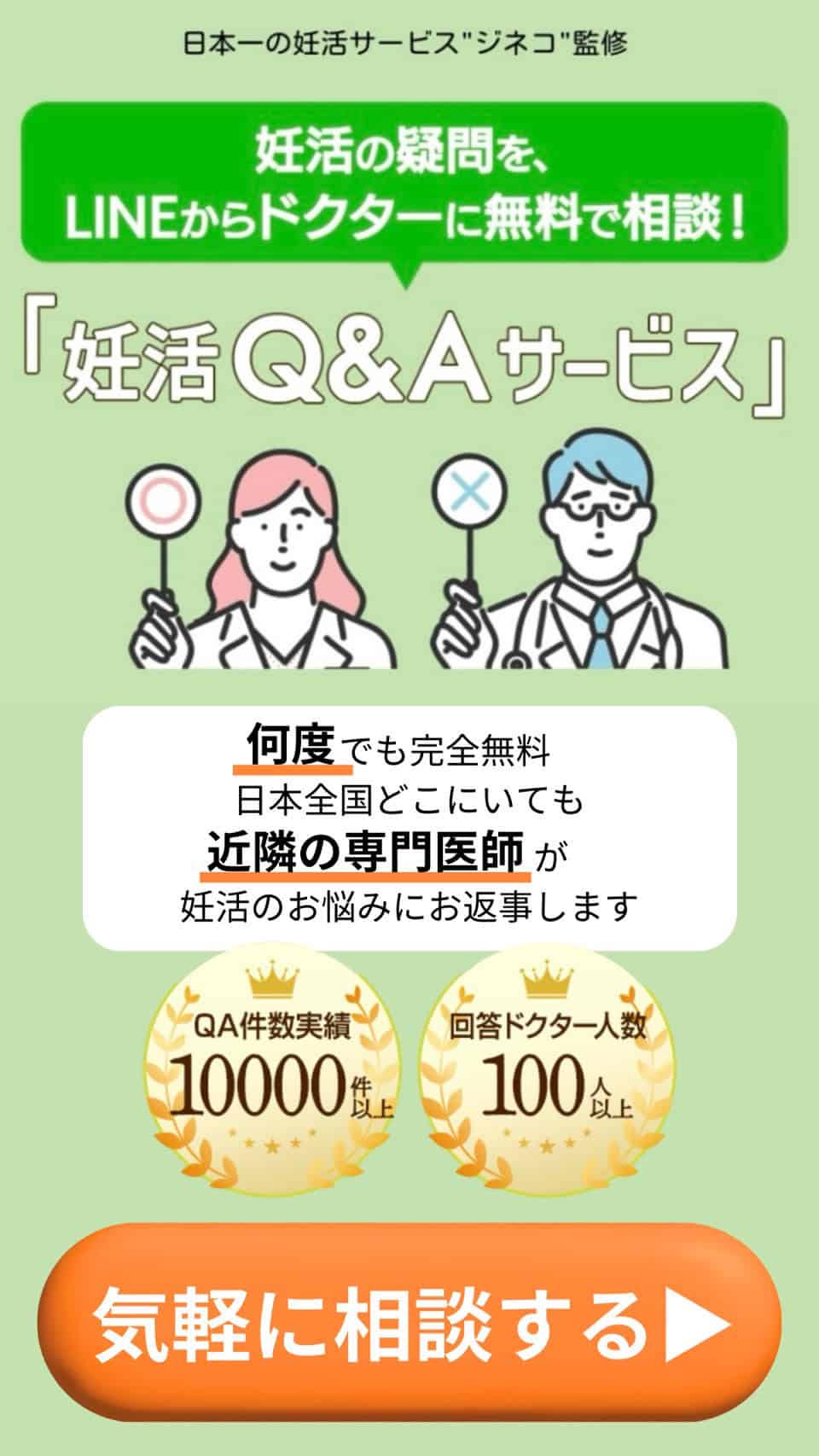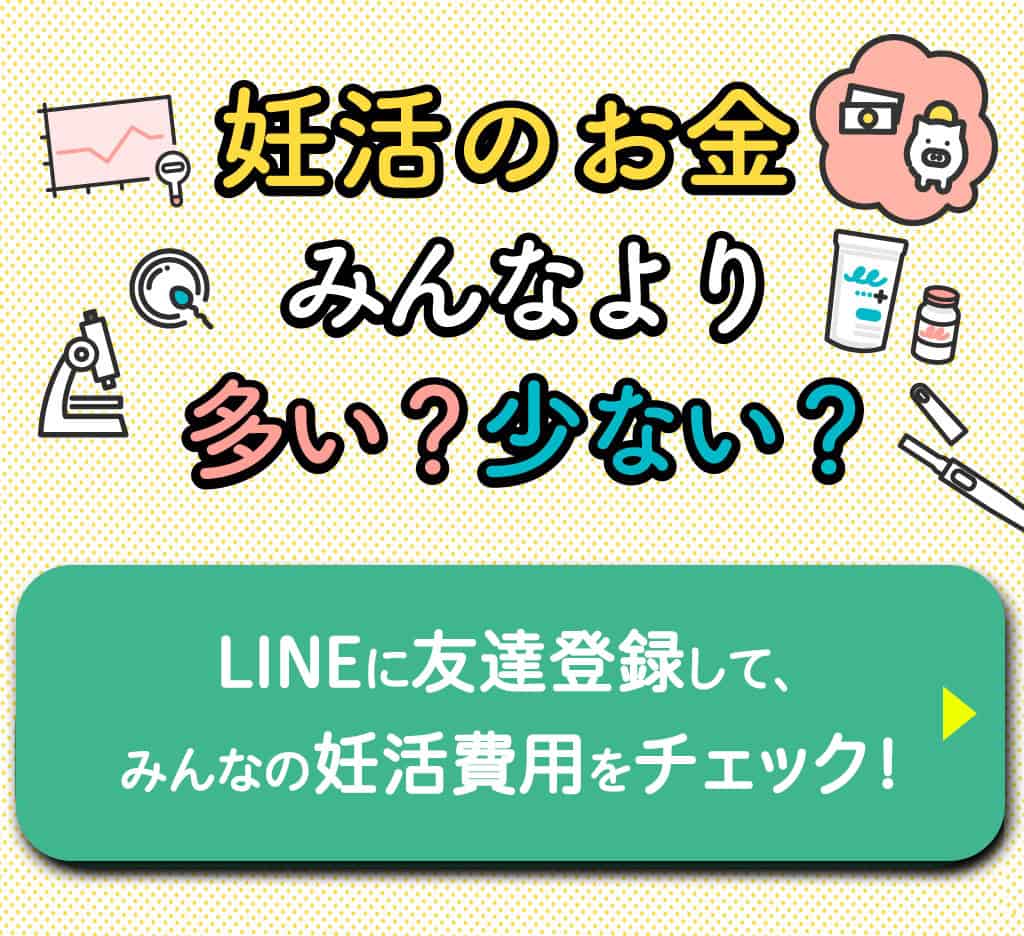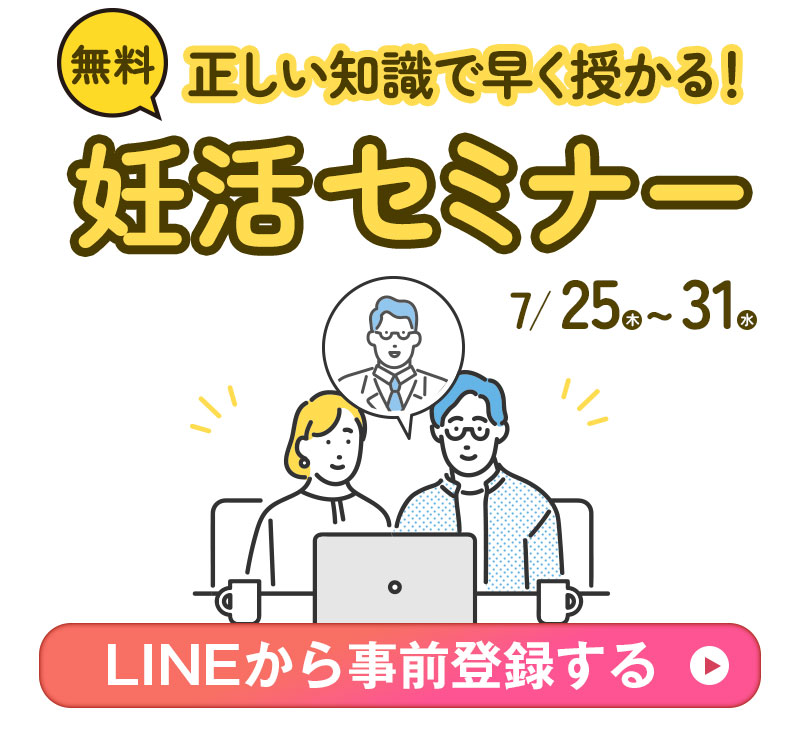豆腐メンタルさん(39歳) 現在、人工授精を5回程実施しています。
こちらのサイトを読んでいると、そろそろ体外受精に切り替えないと、続けてもあまり意味がないのだなと知ったところです。
今回お伺いしたいことは、人工授精の際に排卵誘発剤は必ず使用するものか否かです。
現在処置していただいてる病院では、卵の大きさや尿の値をみてその使用を判断されているようなのですが、当サイトを読んでいると必ず使用しておられる先生も見受けられます。
患者によって、という部分かもしれませんが、一般的に誘発剤使うことのデメリットから使用を控えるというのもあるのでしょうか。
また、使用の判断等はサイズ等からみての「勘」という説明を受けたのですが、それはどの先生もそういうものなのでしょうか。
医療行為にしては原始的というか、根拠がモヤッとしていて、ここで良かったのだろうかと心配になることもあります。
解明できていない部分が多かったとしても、受ける治療に関してはこれで良いのだと安心して任せたい、不妊治療に限らず皆そのように思っているのかなと改めて気付かされた次第です。
何卒宜しくお願いします。
こちらのサイトを読んでいると、そろそろ体外受精に切り替えないと、続けてもあまり意味がないのだなと知ったところです。
今回お伺いしたいことは、人工授精の際に排卵誘発剤は必ず使用するものか否かです。
現在処置していただいてる病院では、卵の大きさや尿の値をみてその使用を判断されているようなのですが、当サイトを読んでいると必ず使用しておられる先生も見受けられます。
患者によって、という部分かもしれませんが、一般的に誘発剤使うことのデメリットから使用を控えるというのもあるのでしょうか。
また、使用の判断等はサイズ等からみての「勘」という説明を受けたのですが、それはどの先生もそういうものなのでしょうか。
医療行為にしては原始的というか、根拠がモヤッとしていて、ここで良かったのだろうかと心配になることもあります。
解明できていない部分が多かったとしても、受ける治療に関してはこれで良いのだと安心して任せたい、不妊治療に限らず皆そのように思っているのかなと改めて気付かされた次第です。
何卒宜しくお願いします。
滝口修司先生に聞いてみました。

【医師監修】IVFクリニックひろしま滝口修司先生 山口大学医学部医学科卒業。山口大学医学部附属病院、済生会山口総合病院、正岡病院などの勤務を経て、2012年より浅田レディースクリニックに勤務。2017年1月、故郷・広島の玄関口である広島駅前に「IVFクリニックひろしま」を開院。
※お寄せいただいた質問への回答は、医師のご厚意によりお返事いただいているものです。また、質問者から寄せられた限りある情報の中でご回答いただいている為、実際のケースを完全に把握できておりません。従って、正確な回答が必要な場合は、実際の問診等が必要となることをご理解ください。
目次
・人工授精で排卵誘発剤を使う理由について教えてください。
一般的に、人工授精単独よりは卵巣刺激併用による人工授精の方が妊娠率、生産率が高いことが知られています。ただし、多胎妊娠や卵巣過剰刺激症候群の発生リスクが高まる可能性も念頭に置く必要があります。
・人工授精で排卵誘発剤を使わないケースはありますか?
上記の理由から、排卵誘発剤を必ずしも使う必要はありません。「豆腐メンタル」さんが人工授精を5回実施しても妊娠に至っていないのであれば、手を変えるという意味で、排卵誘発剤を使用してみても良いかも知れませんが、これが妊娠に至っていない主原因ではないと思います。
・排卵誘発剤を使用するかどうかを決める基準はありますか?
特に基準はありませんので、「豆腐メンタル」さんの主治医の先生のおっしゃる「勘」は決して間違いではありません。あくまでも、多胎妊娠や卵巣過剰刺激症候群のリスクと、排卵誘発による妊娠率向上の期待度、この両者のバランスで判断することが大切です。
・現在、人工授精を5回実施していますが、体外受精にステップアップしたほうがよいと思われますか?
はい。生殖補助医療へのステップアップが望ましいと考えます。当院では、人工授精は4回までにとどめることをお勧めしています。ご年齢やAMHの値によっては、もっと早めのステップアップも考慮します。

・その他、アドバイスをお願いします。
あくまでも私見ですが、ステップアップが早すぎたと後悔するご夫婦に会ったことはありません。逆に、もっと早くステップアップすれば良かった、もっと早く転院して来れば良かった、と後悔するご夫婦ばかりと言っても過言ではありません。
また、生殖補助医療の保険適用の回数制限についても留意されることをお勧めします。「豆腐メンタル」さんは今39歳とのことですが、40歳になる前に生殖補助医療の治療計画を立てて治療を開始することが重要かも知れません。早急に主治医の先生にご相談ください。
ご夫婦で相談しながら、どうぞ前向きに頑張ってほしいと思います。