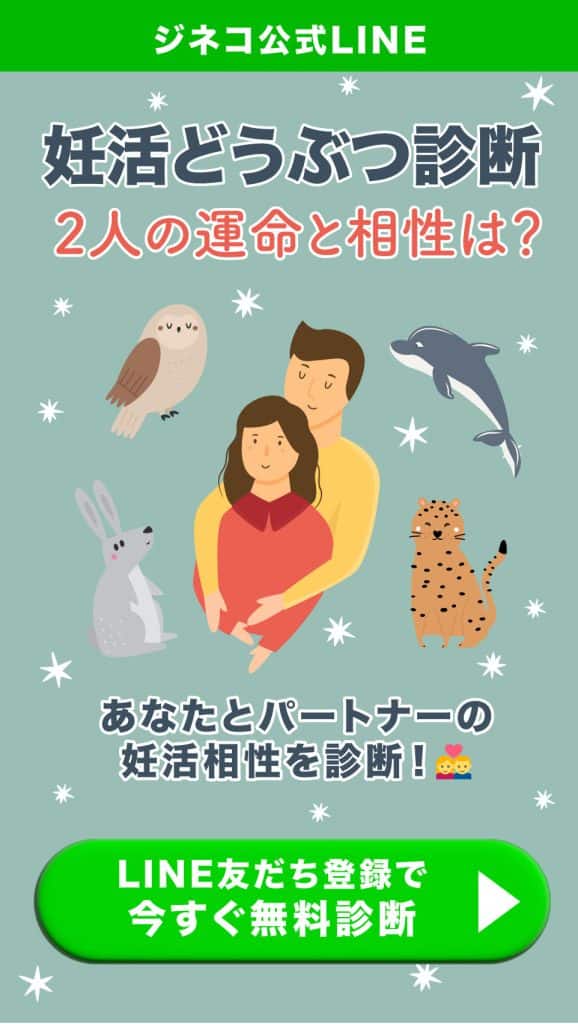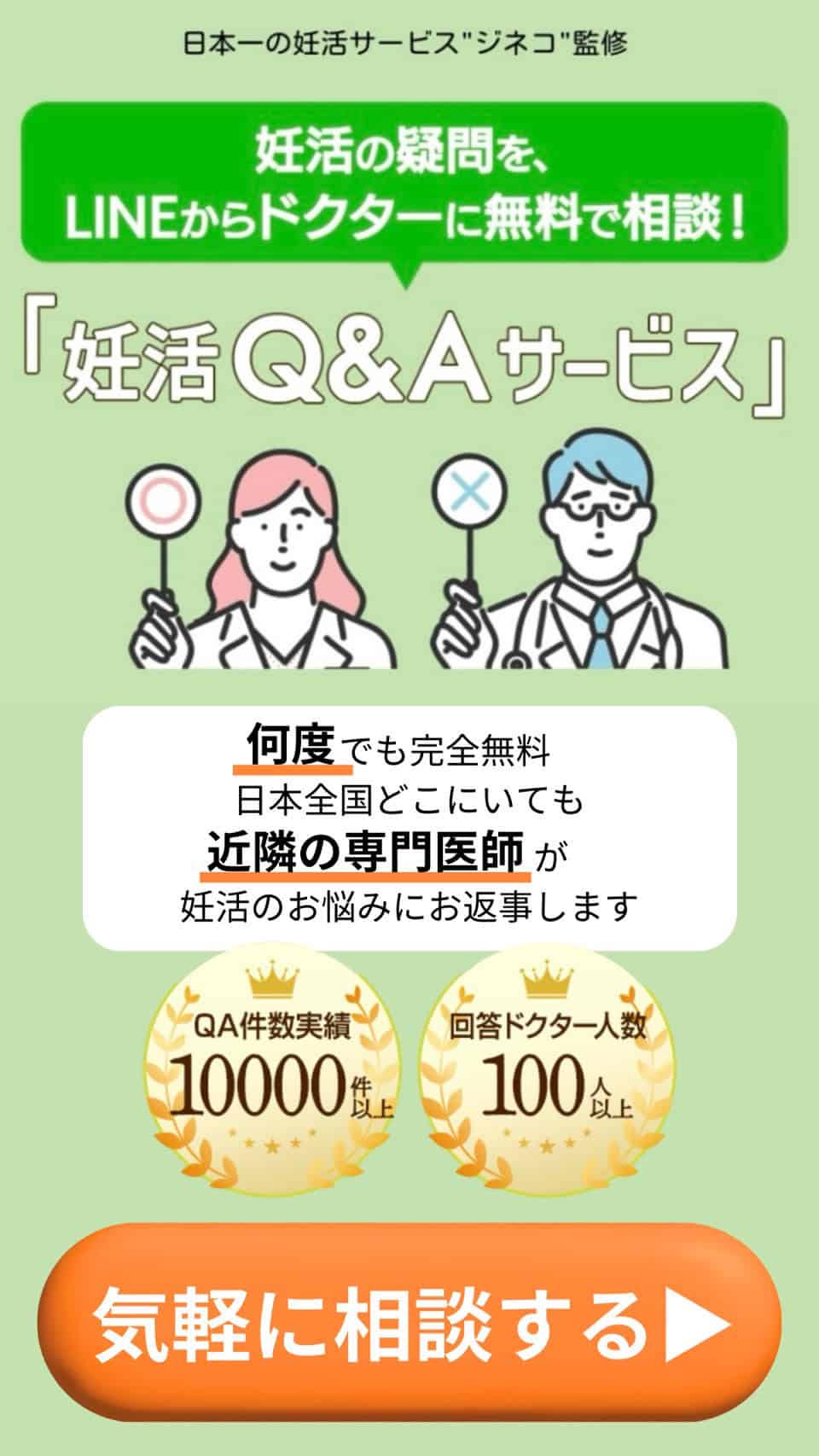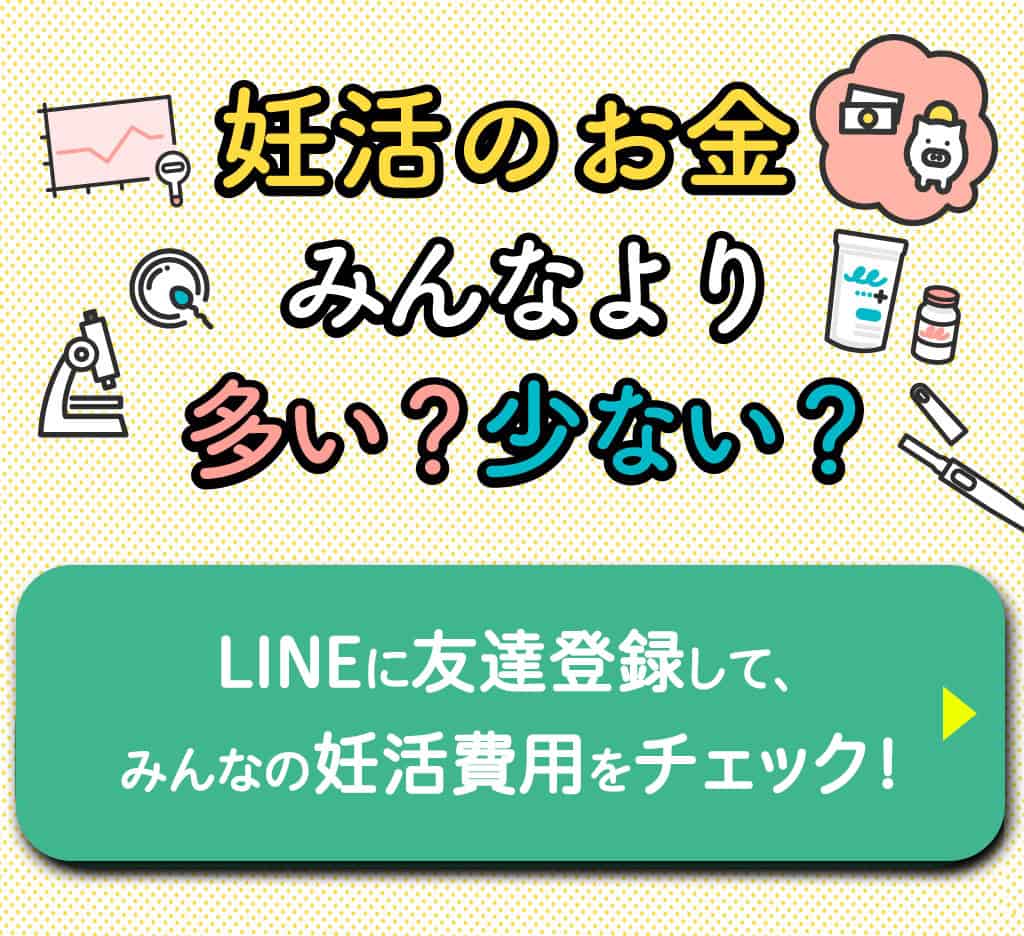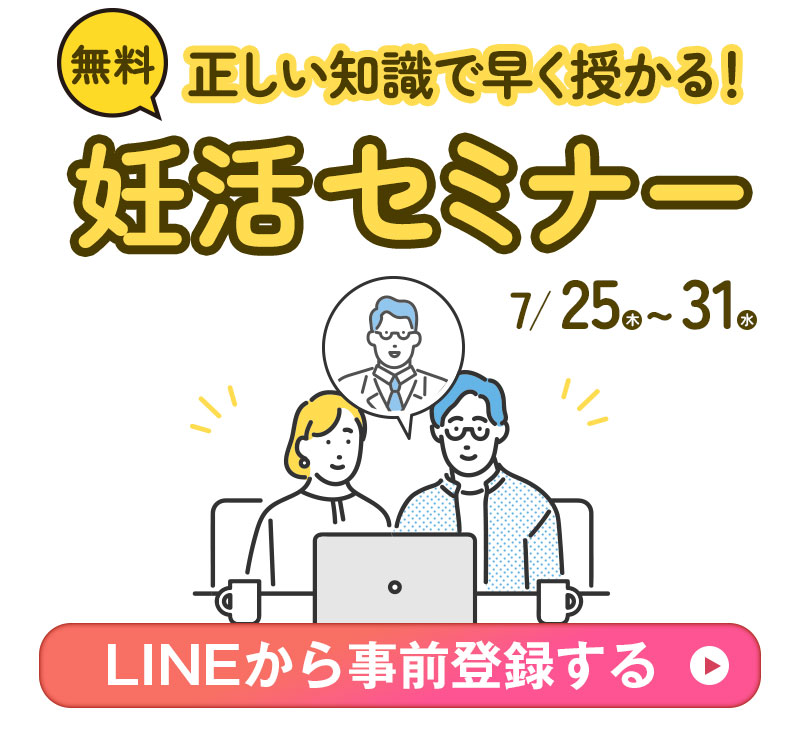田村秀子先生の心の玉手箱Vol.40
死産や治療の不成功が続き、気持ちを奮い立たせようとしても、これからの治療への不安と、友人の妊娠や心ない言動に心が折れそうです。どうすれば前を向けるでしょうか? 秀子先生にお聞きしました。

お子さんはあなたが悲しむことを望んで天にいったのではありません
にじさんが初盆、出産予定日(お誕生日)といって、失ったお子さんに気持ちが向いているうちは、次の赤ちゃんは遠いかな。亡くなったお子さんは、そんなことを望んで天にいったわけではないと思います。
親の死もそうです。私は両親と義父を亡くしましたが、親を見おくるたびに「ああしてあげればよかった」と悔やみます。でも親はそんな姿を望んでいるでしょうか。「あなたはちゃんとやってくれた」と思ってくれているはずです。
天にいるお子さんは、この世よりも高みの尊い存在として、あなたを見守ってくれていると思います。ですから、「わが子は残念ながら天にいってしまったけれど、私たちを見守り、力をくれている。だから、そのうち赤ちゃんを授かれるはず」というふうに、自分の人生の台本を書いて、前進されてはどうでしょうか。そうしなかったら、亡くなったお子さんに申しわけないと思うのです。「私(僕)が生まれてあげられなかったために、お母さんがこんなに苦しんでいる」と、心配をかけているかもしれませんよ。

自分が幸せになるための台本に書き換えましょう
流産した患者さまにも、「天にいったお子さんはあなたを苦しめたり、悲しませたりするためではなく、天から見守るという守護霊のような役割をもって、ここに来たのだと思います。だから、いつもその子に見守られていると思ってはどうですか?」とお話ししています。
自分を鼓舞するような台本に書き換えることはいくらでもできます。とはいえ、台本はあくまでも台本ですから、現実に立ち返った時に涙があふれることもあります。失ったものを忘れることはできないし、二度と会うこともできないのです。自分の気持ちを切り替えるしかありません。

にじさんも自分が書いた台本を読み返し、天にいるお子さんに助けてもらいながら、「また明日から頑張って生きよう」というふうに考えていきましょうよ。自分のもとにきてくれた子どもが、自分のために尽くしてくれると思えたら、もっと楽になるのではないでしょうか。
採卵や胚移植のたびに「また、うまくいかないのでは…」と不安になるのは自然なことです。それを感じないようにするのではなくて、次は、天にいるお子さんに「○○ちゃん、見守っていてね」と話しかけながら、お守りのようなものを握りしめて採卵や移植に臨むといいと思います。それでもうまくいかなかったら、次はもっと大きな心の声でお願いしてみましょう。
お友だちについては、本音でぶつかることなく、そのままの関係を続けていくのであれば、静観するのが一番。ただ、心の中ではちょっと悪い人になって「江戸のかたきは、長崎で討つ」な〜んて想像するだけで、気持ちが軽くなりますよ。