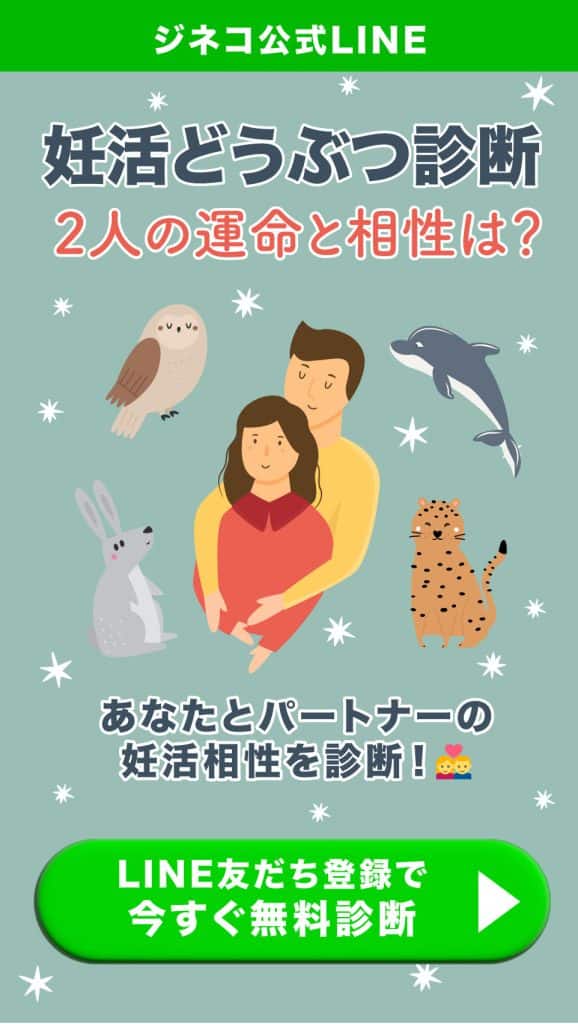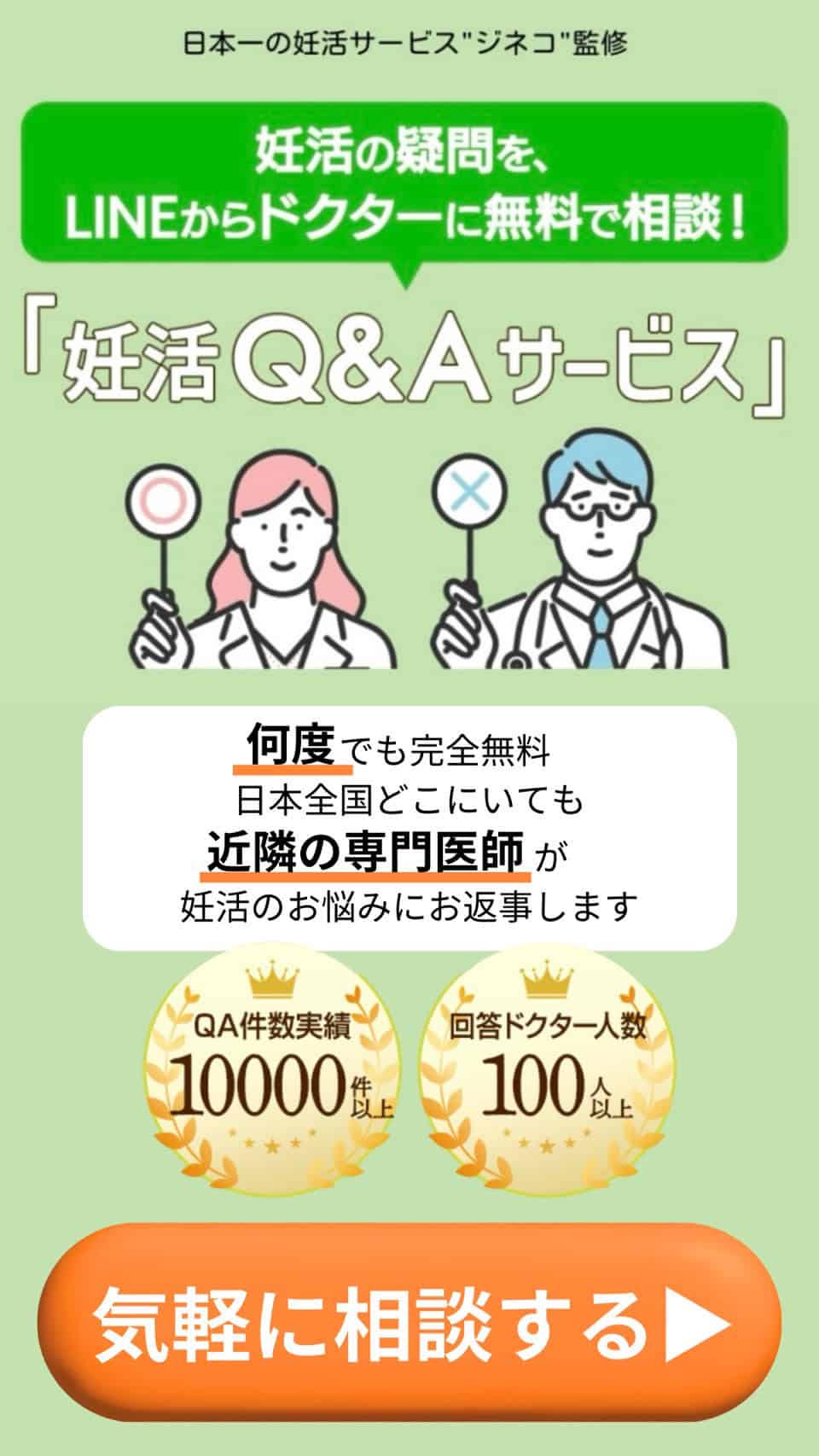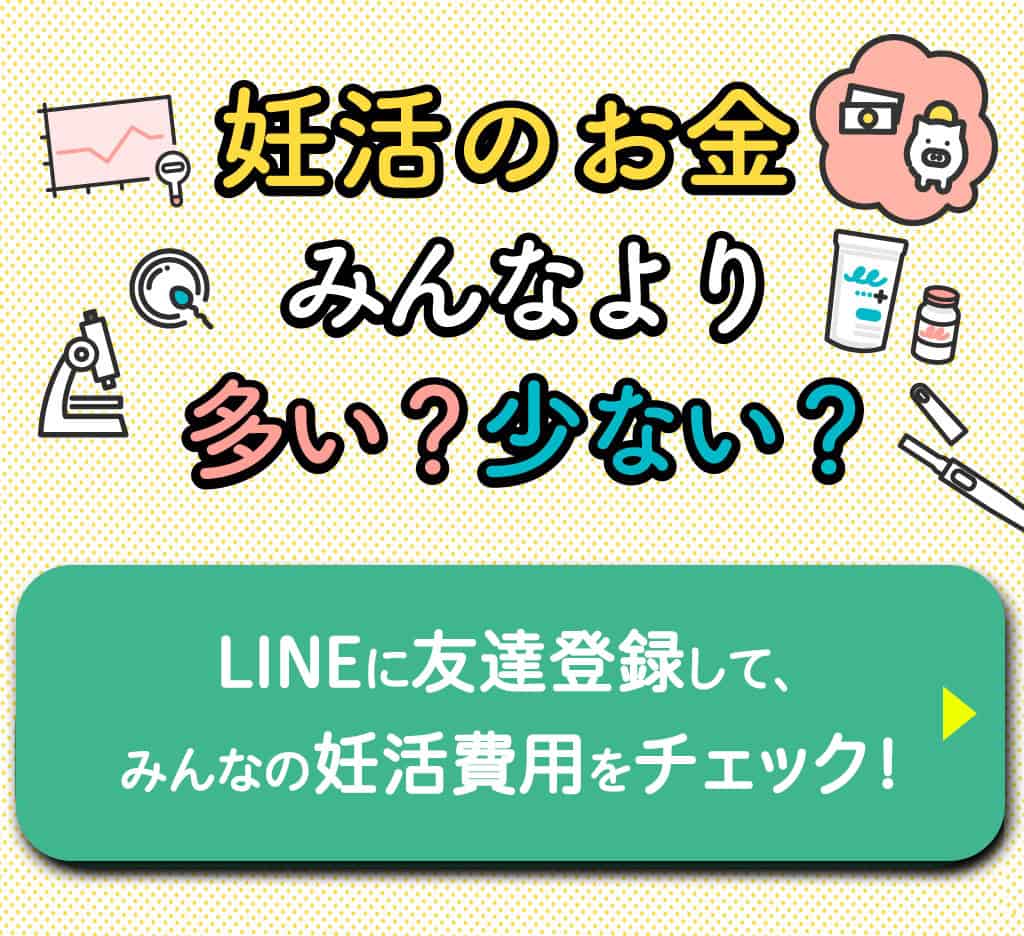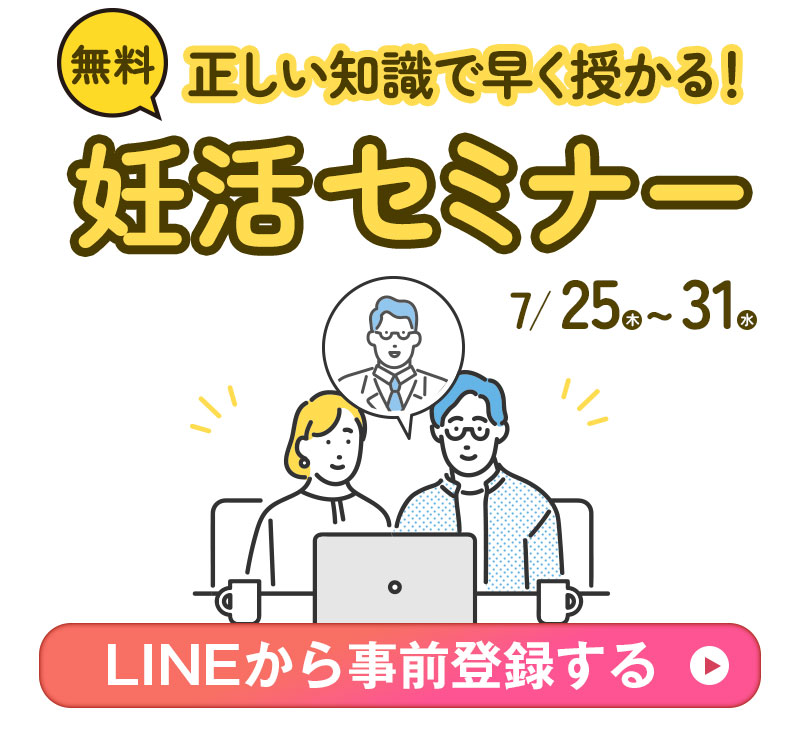基本方針は、初回は分割胚、 2回目以降は胚盤胞移植。 着床環境や受精卵について 問題点を絞り込みます

治療ステップは、さまざま
患者さんによって、さまざまな状況があると思いますが、先生の治療方針についてお聞かせください。
内田先生 基本となる治療ステップはありますが、患者さんは十人十色、10 人いたら 10 人のプログラム、治療の方針があります。

不妊の原因やご夫妻の年齢などを加味し、じっくりお話ししながら治療を行うことが大切です。
医療側が一方的に治療方針を決定するのではなく、患者さんご自身が「どう進めていくのが自分たちに最も合っているのか」という決定ができるよう、情報提供とサポートに努めています。
胚盤胞移植が完全ではない
分割胚と胚盤胞、新鮮胚と凍結胚など、移植する受精卵の条件についてはいかがでしょう。
内田先生 当クリニックでは、初回は分割胚による移植、2回目以降は胚盤胞による移植を基本とし、胚盤胞移植に重点をおいています。

なぜなら人工的な培養環境で胚盤胞にまで到達できた受精卵は、妊娠への可能性が高い良好な受精卵と考えられるからです。
ただし、これもケースバイケースです。
38 歳以上と年齢が高めの方や、AMHの値が 10 未満で卵巣予備能力が低下している方など、時間的な余裕がない方の場合は、最初から胚盤胞での移植をおすすめすることがあります。
分割胚移植の場合でも、その周期で移植しなかった余剰胚を胚盤胞へと追加培養し、凍結保存しておくことをおすすめしています。
とはいえ胚盤胞移植は、ここ6〜7年で一般的になった新しい治療法であり、私は胚盤胞だけがすべてとは考えていません。
たとえば、胚盤胞移植では着床せず、3日目の8分割胚を移植して妊娠につながったというケースもあります。

また、胚盤胞移植は5日目に行うのが通常ですが、6日目で初めて胚盤胞に到達する成長の遅い受精卵も、受精率は下がるものの、妊娠の可能性がまったくないというわけではありません。
融解胚移植のタイミング
凍結胚の融解胚移植を行うタイミングについて、先生はどのように考えていらっしゃいますか。
内田先生 原則として、子宮内で受精卵の着床の準備ができた時、すなわち妊娠成立の条件が整った時に胚を移植しようというのが、凍結融解胚移植の考え方です。
たとえば自然周期で排卵が確認できた場合、その2〜3日後に胚移植が可能です。
しかし、排卵が順調ではない時や、排卵があったとしても、着床期の条件がよくない黄体機能不全の方などには、排卵誘発剤の使用が有効となります。
さらにホルモン補充周期により、排卵後の着床環境を人工的につくり出すことも可能です。

ホルモン剤を使用する期間をあらかじめ定めておいて、子宮内膜の条件と血中のホルモンの値を測定しながら、着床環境が最も整った時に移植します。
この方法は排卵周期が不順な方に大変有効です。
着床環境、受精卵の条件など、さまざまな要因に注目されるのですね。
内田先生 はい。培養液や培養器などの培養環境も重要なファクターです。
当院でも培養環境に問題が起こらないように努めていますが、現状に満足することなく、培養液の選択や最新の機器の導入には常にアンテナを張っています。
着床や受精卵の条件、培養環境など、問題点を丁寧に一つずつ絞っていくことが治療において重要だと考えています。
※分割胚と胚盤胞:分割胚は、受精後2~3日目の胚で、4分割から8分割した状態。4分割胚、8分割胚という。胚盤胞は、受精後4~6日目の胚で、自然妊娠ではちょうど子宮に着床する頃にあたる。