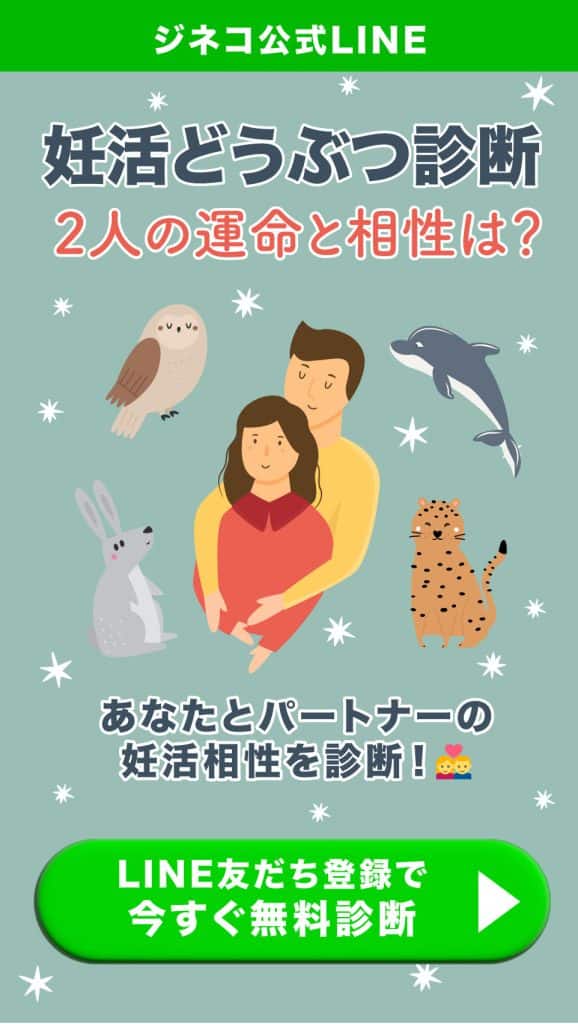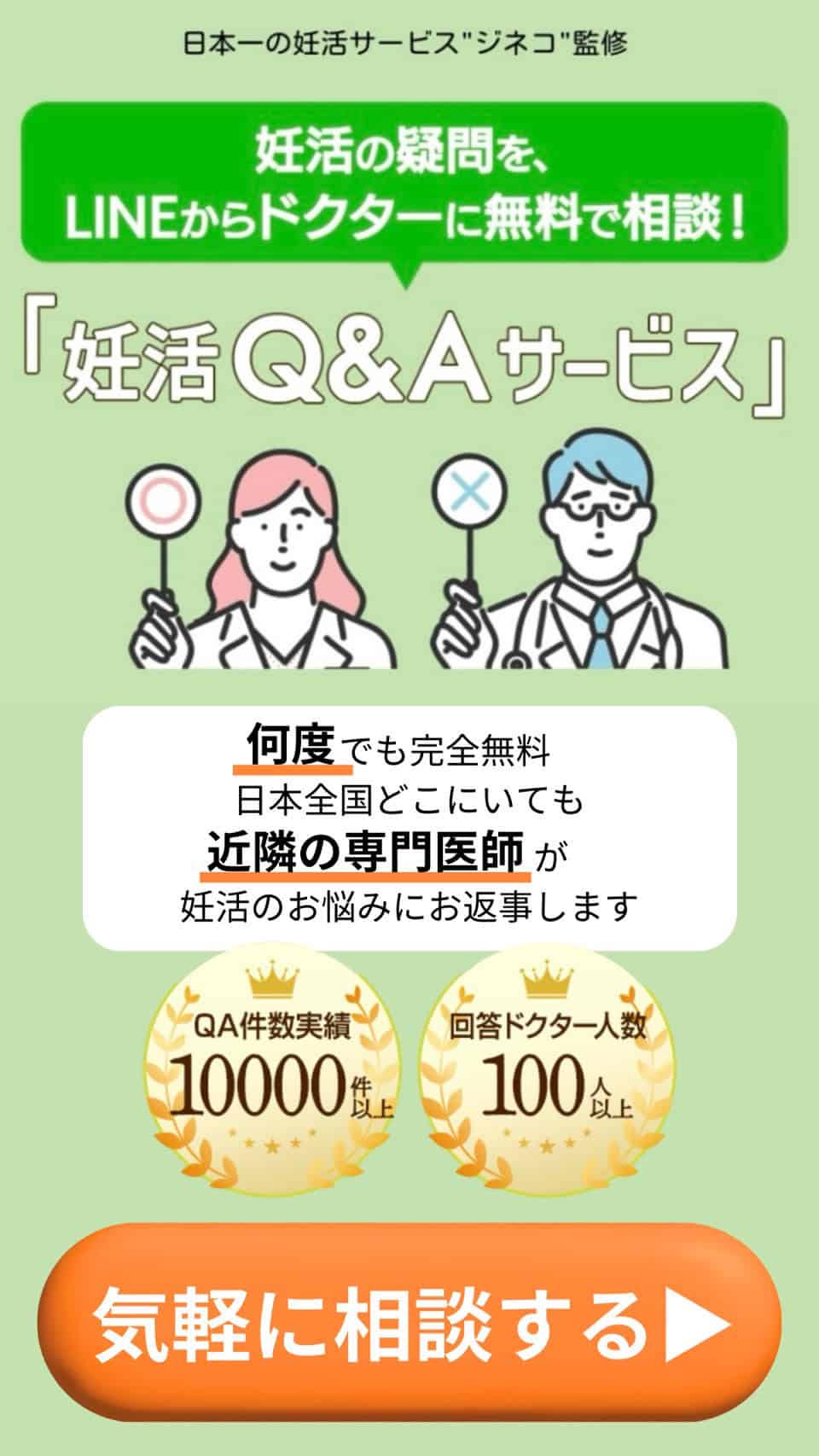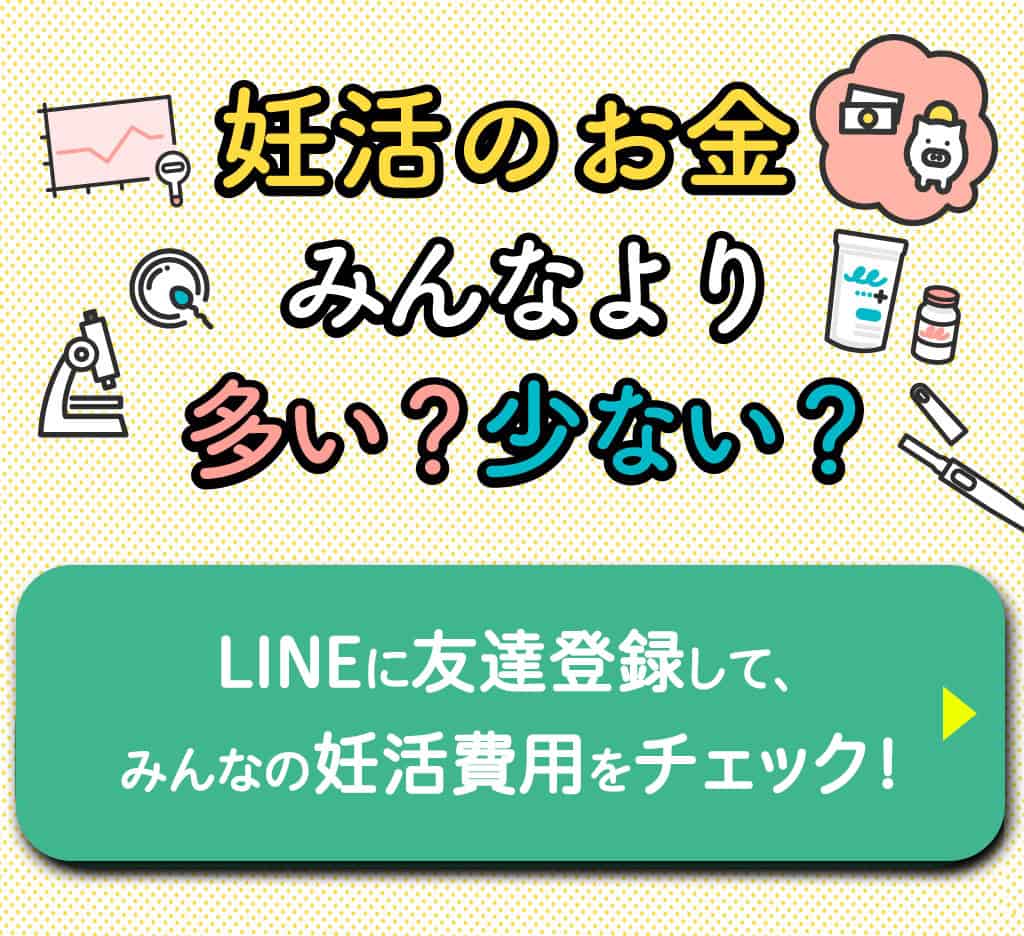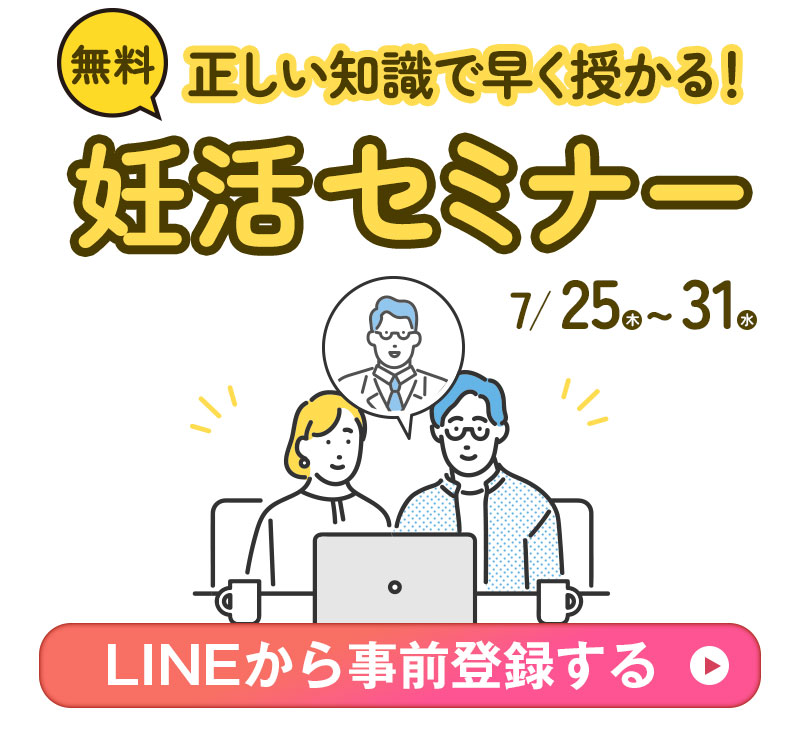不妊治療に携わることになった理由や それにかける想いなどをお聞きし、 ドクターの歴史と情熱を紐解きます。
家族が増える喜びを 多くの人に知ってほしい ・・・・・・ それが、僕の想いの原点
出産の素晴らしさを知り、決意した生殖医療への道
まず、内田先生が生殖医療を志すことになったきっかけを教えてください。
内田先生 1978年にイギリスで、世界初となる、体外受精児が誕生しました。
そしてその数年後に、日本でも東北大学で生殖医療への取り組みが始まりました。
その頃から、僕もそういった医療に関わってみたいなという漠然とした気持ちがあったんです。
その後、僕が通っていた島根大学でも生殖医療が始まり、僕はその年に大学院へ進学して、体外受精の研究に取り組みました。
その時、島根県で初めてとなる、体外受精による出産にも携わるという経験をしました
本格的に、生殖医療の道に進むことに決めた出来事があったのでしょうか?
内田先生 大学院を出て、研修医になってからは、産科の先生のところでお世話になっていました。
お産に並々ならぬ情熱を注いでいる産科の先生の下で学んだのですが、お産の時、赤ちゃんが無事生まれて、僕が分娩室からご家族が待っている待合室に出ていくと、ご主人もご家族も本当に嬉しそうな顔をしていらっしゃるんですよ。
その場面に立ち会って、子どもが生まれて家族が増えることの素晴らしさを心から実感しました。
しかし、その一方で、そういう状況に立ち会えない、不妊で悩んでいる人たちがいる。
そういう人たちのために、自分ができることをしたいと強く思うようになったんです
偶然が重なった 忘れられない胚移植
そうした思いから、ご自身のクリニックを開くことになったのですね。
内田先生 そうですね。
開業までの準備中は、知人の病院の産婦人科の中で、体外受精に必要な設備をそろえて、患者さんに体外受精を行っていたんです。
しかし、それがなかなか成功せず、試行錯誤の日々が続いていました。
そして、いよいよクリニックを開設する場所が決まり、工事が始まる前日、患者さんに胚移植をすることが決まっていた日の朝に、病気の母が亡くなったのです。
僕は自分で母の死亡診断書を書いた後、予定通りに胚移植を行いました。
それが、僕が一人で行った体外受精における、最初の妊娠成立となったのです。
母が亡くなったのと同じ日に……。
偶然かもしれませんが、母が、この仕事を続けてきたことに、そして開業することに大きな意味を与えてくれたような気がしました。
忘れられない1例目の妊娠成立でした
お母様が背中を押してくれたのですね。理想のビジョンはあったのですか?
内田先生 開業前に勤務していた島根大学附属病院では、当時、体外受精の件数が年間 30 ~ 40 件。
そのうち妊娠成立するのは1~2人でした。
妊娠から疾病まで診察しながら、学生指導もしていたので、生殖医療に力を入れたくても難しかった。
ジレンマがあったんです。
そこで、生殖医療に専念しようと決心しました。
そんな時に、広島HARTクリニックで行われていた〝IVFアットオフィス〟という診療スタイルを知ったんです。
システム化されたこの方法なら、患者さんが多くの時間を割かずに、効率的に治療に取り組むことができます。
実際に、妊娠率もどんどん上がっていました。
そこで、不妊治療だけに集中して取り組めば、小さなクリニックでも結果が出せるのだと確信し、そういうクリニックを目指していこうと強く思いました
これまで内田先生を支えてきたのは、どんな思いだったのですか?
内田先生 できるだけの治療をしたけれど妊娠できなかった人たちを、何とかしてあげたい。
たとえ妊娠できなかったとしても、患者さんが納得して治療を終えることができるクリニックにしたいという思いで一生懸命やっていましたね。
その当時、大きな支えだったのが、同じ島根県で産科を開院している先輩でした。
その先輩は、不妊症の患者さんが来院した場合に、僕のクリニックを紹介してくれて、その患者さんが妊娠したら先輩の産科に戻っていくという、〝産科と不妊クリニックの分業と連携の体制〟を組んでくださったんです。
現在は、当院も不妊専門クリニックとして認知され、より多くの病院と連携が取れるようになりました
僕の原点の幅を広げる 今後の活動
今後の課題や、展望をお聞かせください。
内田先生 僕はこれまで、不妊症に真剣に向き合うたくさんのご夫婦を、間近で見てきました。
そういったご夫婦に、子どもが生まれて家族ができる、その素晴らしさを何とか体験してほしい。
そう願って、僕のありったけの力を注いでいます。
不妊治療は今、創成期から安定期を経て、より上を目指していく段階です。
現場では、スタッフ、特に胚培養士の養成と確保が課題となっています。
胚培養は専門性の高い分野ですから、しっかりした養成機関の整備や、国家資格の必要性も感じています。
また、医療技術が進歩する一方で、どんなに手を尽くしても、妊娠できないご夫婦がいるという現実もあります。
生殖医療の根本を〝家族をつくること〟と考えた時、選択肢を〝里親〟や〝養子〟という制度まで広げれば、〝家族が増える喜びを少しでも多くの人に知ってほしい〟という僕の原点に、さらに幅を持たせることができるのではないかと思っています。
不妊治療で子どもを授かれなかった方のために、もっと行政側と患者サイドをうまくつなげられるよう、里親などの制度を勉強し、できることをしていきたいと考えています